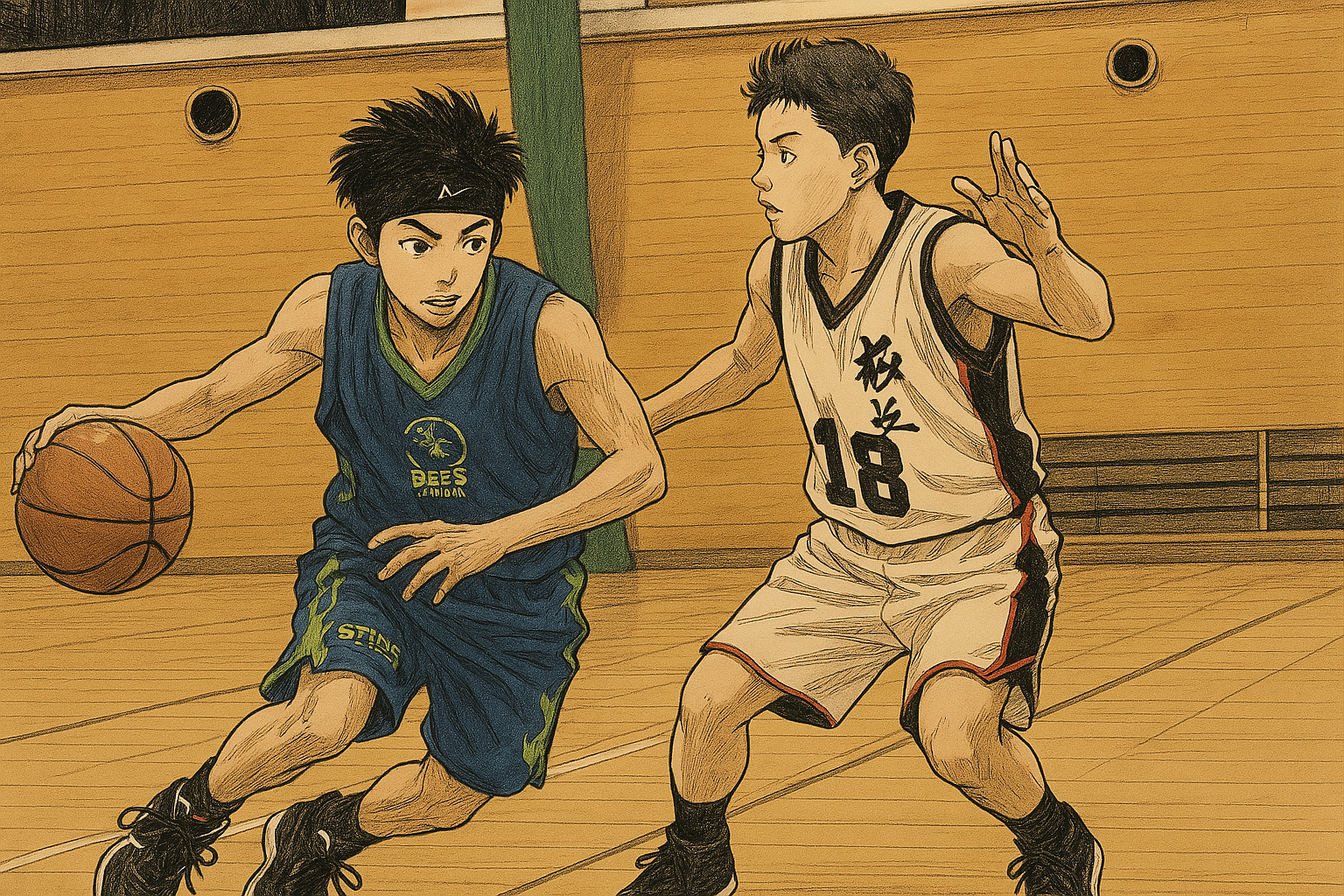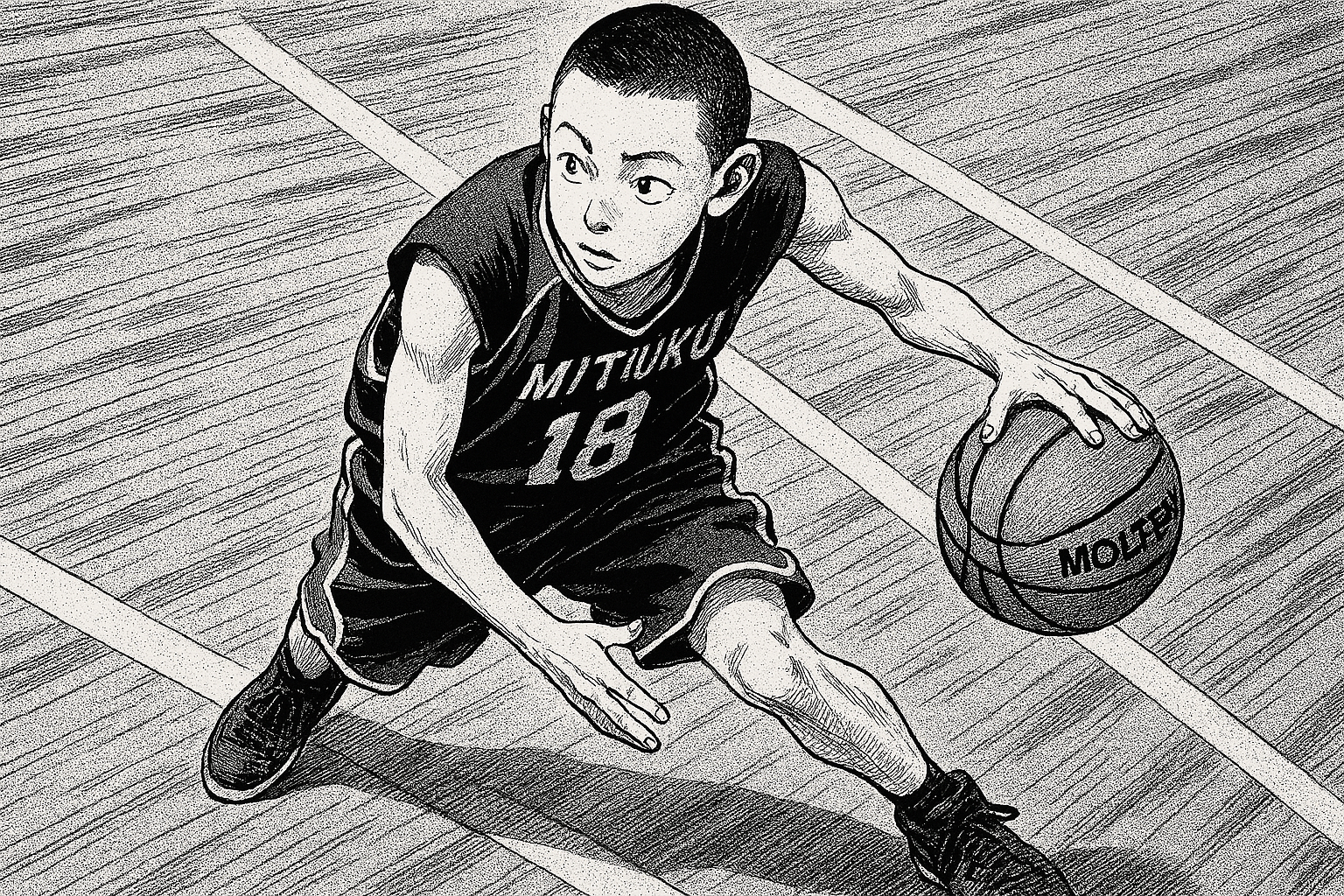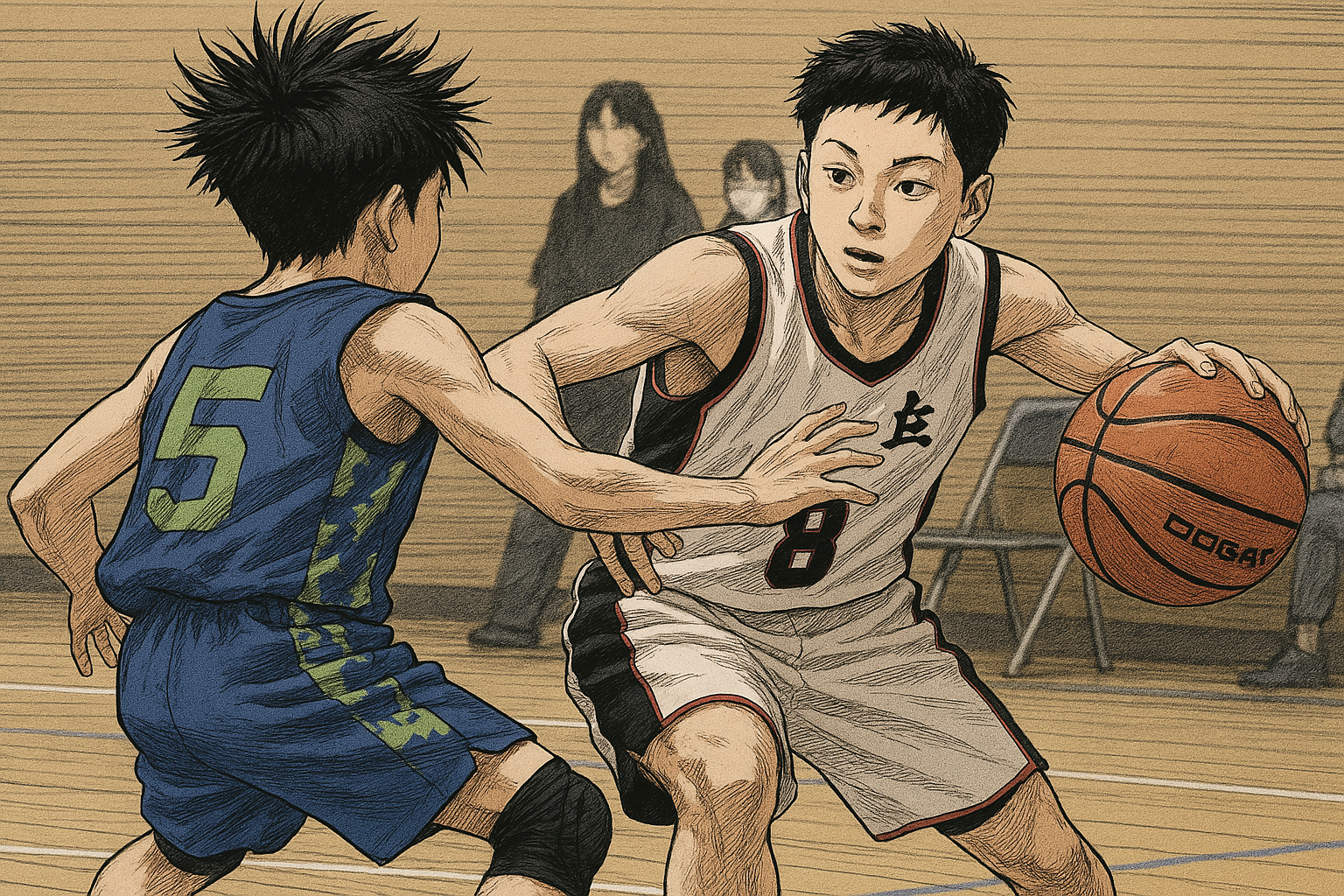みなさん、こんにちは!今回は、中高生バスケの現場で昔から当たり前のように取り入れられてきた「持久走中心のトレーニング」について考えてみたいと思います。特にアメリカやスペインなど、バスケ先進国と呼ばれる国々ではどんなフィジカル強化が行われているのかを踏まえながら、「そもそも長距離走はバスケットボールの試合に必要な体力づくりに合っているの?」という疑問を掘り下げていきます。
背景と課題
まず、日本の小学・中学・高校世代(U12〜U18)を対象にしたバスケットボール指導では、スタミナ強化を狙って持久走(長距離ランニング)など、いわゆる「走り込み」が盛んに行われていますよね。これは基礎的な持久力や精神力を鍛えることを狙ったものですが、実際の試合で必要となるゲーム体力に直結しているのかどうか、疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。
特に欧米の先進的な育成現場を見てみると、日本のように延々とボール無しのランニングを続けるケースはあまりないといわれています。そこで今回のテーマでは、持久走中心の練習が本当にバスケに合ったやり方なのかという点を、アメリカやスペインなどのユース育成事情と比較しながら、具体的なメニュー例を交えてご紹介します。
バスケットボールに求められる体力要素
バスケの試合をイメージしてみると、コートを走り回っている時間は長いものの、実際のプレーは数秒間のスプリントやジャンプといった高強度の動作を何度も繰り返す形ですよね。5〜6秒ほどの全力プレーと短い休息・低強度動作をセットで延々と続けていくのが試合の実態です。
このとき、1回の全力スプリントにおける有酸素エネルギー供給の割合は10%未満との報告もあり、ほとんどが無酸素的エネルギー(ATP-CP系・解糖系)から生み出されます。それでも連続スプリントを何度も行う過程で回復は不十分になり、だんだんパフォーマンスが落ちてくるわけです。なので、繰り返し高強度の動きを続けるための無酸素性パワーと、それを支える有酸素的な持久力の両方が必要ということになります。つまりバスケの体力要件って、インターバル的(断続的)な無酸素運動と有酸素的な回復がセットになっているのが特徴なんです。
持久走中心の練習の効果と問題点
日本では長い距離を走らせたり、ひたすら走り込みをさせたりする練習が昔から盛んですが、これは確かに有酸素持久力の向上や精神的タフネスの育成には寄与します。特に試合終盤になってもバテずに走り続けられる土台づくりには役立ちますよね。
ただし、バスケットボール特有の敏捷性や瞬発的な反復力は、同じペースでただ走るだけではなかなか伸ばしきれません。アメリカの指導者向け資料には「一定ペースの長距離走はコンディショニングの基礎作りにすぎず、試合のスピード感に対応するにはインターバルトレーニングが欠かせない」とハッキリ書かれているくらいです。たとえば、1マイル(約1.6km)を7分ペースで走る練習を積んだとしても、速攻で一気に走り抜けるスピードやゴール下で身体を当て合うパワーまではつきづらいですし、試合終盤に一瞬でギアを上げなきゃいけない状況などには対応しにくくなるでしょう。
さらに「走り込みが足りないとスタミナも根性もつかない」という、いわゆる精神論的な考え方から、ボールを使わないフィジカルトレーニングに時間を多く割くやり方もよく見られます。ところが、そうした単調な体力練習ばかりだと、選手が飽きてしまうリスクもありますし、そのぶんスキル練習や戦術練習の時間が削られることにもなります。コーチ留学でスペインに行った方の話では、日本の練習はフットワークやランニングばかりで「まるで軍隊式だ」と感じる人もいるそうですが、スペインだとウォーミングアップからゲーム形式を取り入れるなど、楽しさを活かしながら効率的にトレーニングしているケースが多いというんです。そう考えると、長距離走自体を否定するわけではなくても、そればかりに偏るのは考えものですよね。
欧米(アメリカ)のユース年代における体力トレーニング
では実際、アメリカのユース(高校やAAUなど)ではどんなフィジカルトレーニングが行われているのでしょうか。大きな特徴としては、持久力をしっかり鍛えつつも、バスケ特有の動きに合わせた「短いダッシュを繰り返す」練習が中心になっている点が挙げられます。
たとえば、20〜30mのスプリントを何本も繰り返すインターバルトレーニングや、コート幅を17往復する「17本ダッシュ(セブンティーンズ)」なんかが定番ですね。実際、試合で何分間もゆっくり走り続けるシーンはほぼないわけですから、長距離走の時間は最小限にし、反復スプリントを中心に据えるという考え方なんです。こうしたインターバル形式のメニューは心肺機能を高めるだけでなく、試合さながらの瞬発力の反復も鍛えられるので非常に効率的です。そのぶんトレーニング時間自体も短くて済むから、浮いた時間をスキル練習に回せるというメリットまであるんですよ。実際、若年層の研究でも、HIIT(高強度インターバルトレーニング)は持久力を上げながら短時間でしっかり追い込めるので、スキルトレーニングとの両立がしやすいと報告されています。
欧州(スペイン)のユース年代における体力トレーニング
スペインでも、日本のように「延々と走り込み」一辺倒のメニューはあまり重視されていません。むしろ、質と機能性に重きを置いたフィジカルトレーニングが中心で、クラブのユースチームなどでは、必要な筋肉を的確に鍛えつつ、コーディネーションを高めるメニューが多用されます。
たとえば筋トレ一つ取っても、何でもかんでも負荷をかけて体を大きくするのではなく、接触プレーに負けない最低限の筋力と、俊敏性を落とさないバランスの取れた身体づくりにフォーカスします。具体的には、ゲーム要素を取り入れたコーディネーショントレーニングや、ラダーやハードルを活用したフットワークドリル、自重・ゴムバンドを用いたサーキットトレーニングなどが盛んです。
こうしたメニューは、選手たちにとって「楽しく、しかも実戦的」であることが重視されていて、ウォーミングアップの段階からミニゲーム仕立てにしてしまうという発想もよく見られます。さらに、5on5をいきなりやらせるのではなく、3on3や4on4でスペースを広く使いながら運動強度を上げる方法も一般的。少人数ゲームは自然と走る量が増えるので、スタミナ強化にもつながるんですよね。
まとめると、欧州のユース育成では持久走は脇役に近い扱いで、代わりに機能性と多様性を兼ね備えたフィジカルトレーニングが重視されているというわけです。
ユース向けトレーニングメニューの例(持久走に代わるメニュー)
「でも実際、どんな練習をすればいいの?」と思われる方も多いかもしれません。そこで、持久走の代わりとして取り入れられるユース世代向けの体力強化メニューを、下の表にザッとまとめてみました。どれもバスケの動きや試合展開に即した形で持久力や俊敏性を鍛えることを目指しています。
| トレーニングメニュー | 内容・目的 |
|---|---|
| インターバル走(高強度-低強度の反復走) | 短い全力疾走と短い休息を交互に繰り返す方法。たとえば「全力ダッシュ30秒+休息30秒×8セット」のように、バスケのプレー感覚に近い形で心肺持久力と反復スプリント能力を効率的に伸ばせます。 |
| シャトルラン(コート往復ダッシュ) | バスケットコートを端から端まで全力ダッシュで往復するドリル。よく知られているのは「17本ダッシュ(17s)」で、サイドライン間を17往復(おおむね1分以内が目安)します。試合中の運動強度に近い負荷を再現しやすく、持久力や敏捷性をまとめて鍛えられるのが魅力。 |
| アジリティドリル(敏捷性・フットワーク系) | ラダー(はしご)やコーンを使ったステップワーク、守備のスライドステップ、バックペダル走など、方向転換やフットワーク向上を狙ったドリル。心拍数を上げながら俊敏さと全身の協調性を一緒に高められるのがメリット。軽い負荷で神経系を刺激し、実戦での素早い攻防に対応できる力を育む。 |
| ゲーム形式トレーニング(少人数ゲーム、連続スクリメージ) | 3対3や4対4などのミニゲームや、時間を切って連続でプレーするスクリメージ(紅白戦)形式での練習。楽しさを確保しながら持久力を高めるだけでなく、実戦さながらの走力・判断力・ゲームIQも同時に鍛えられる。スペイン流では、アップでさえゲーム形式にする工夫がよく見られるそう。 |
| サーキットトレーニング(循環式トレーニング) | 複数のエクササイズを休憩をほとんど挟まずに連続して行う方法。例としては「30秒間の自重スクワット→すぐに30秒間のラインタッチ走→30秒間の腹筋」といった具合に進める。全身の筋持久力と心肺持久力を同時に鍛えられ、短い時間でも高い強度を確保できるのがポイント。自重やチューブを活用したサーキットが重視されている。 |
※もちろん、これらのメニューはあくまで一例なので、年齢やレベルに応じて強度や時間を調整してください。大事なのは、ただ長距離を走らせるのではなく、バスケの動きを意識した短時間高強度の運動を組み合わせることです。
まとめ
日本の中高生バスケで伝統的に行われてきた持久走中心の練習は、有酸素持久力の基盤づくりに役立つ半面、バスケット特有の反復スプリント力や瞬発力の育成という点で十分ではない可能性があります。これに対してアメリカやスペインなどのバスケ先進国では、インターバル走やアジリティドリル、ゲーム形式の練習を使って、効率的にスタミナアップを図る手法が一般的です。こうした方法は試合の動きに直結する体力を養えるほか、限られた練習時間でスキルや判断力を伸ばす余裕も作りやすいメリットがあります。研究でも、短時間高強度トレーニング(HIITなど)は持久力向上に非常に効果的で、余った時間で技術練習を充実させるのに向いているという報告もあります。
結局、ユース世代の体力づくりでは、「質の高いトレーニング」と「バスケならではの動きへの適応」を同時に満たすことが大切なんですよね。長距離走をまったくやらなくてもいいわけではありませんが、常に「これが本当に試合の動きに近いのか?」という視点を忘れずに、インターバル練習やファンダメンタルドリルなどとバランス良く組み合わせることがポイントでしょう。そうすれば、試合で走り負けしないだけでなく、必要な局面で瞬時にスピードを上げたり、終盤でも切れのあるプレーを続けられるようになります。最終的には技術や判断力も含め、総合的なレベルアップが期待できるはずです。
参考文献・情報源:
- バスケットボール指導者向けトレーニングガイド
- 米国コーチングサイトの記事
- 最新のスポーツ科学研究
- スペインの育成現場レポート
- 指導者インタビュー
これらの信頼性の高い情報をベースにして、日本で慣習的に行われてきた持久走偏重の練習を客観的に検証し、海外の事例も交えつつ、より実戦的なトレーニング法を提案してみました。ぜひ一度、チームの練習メニューを見直すきっかけにしてみてくださいね。皆さんのバスケライフが、もっと充実したものになるよう応援しています!