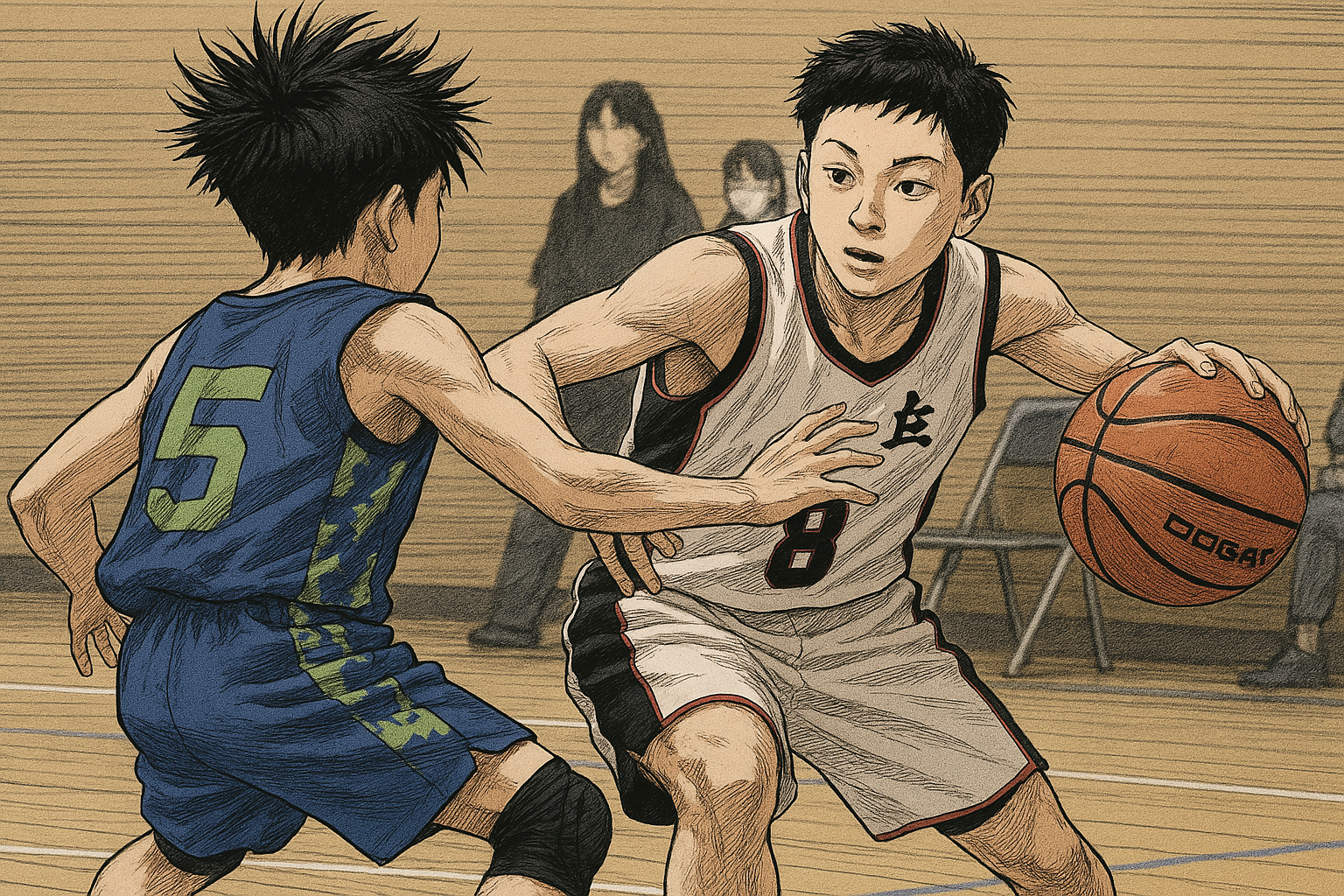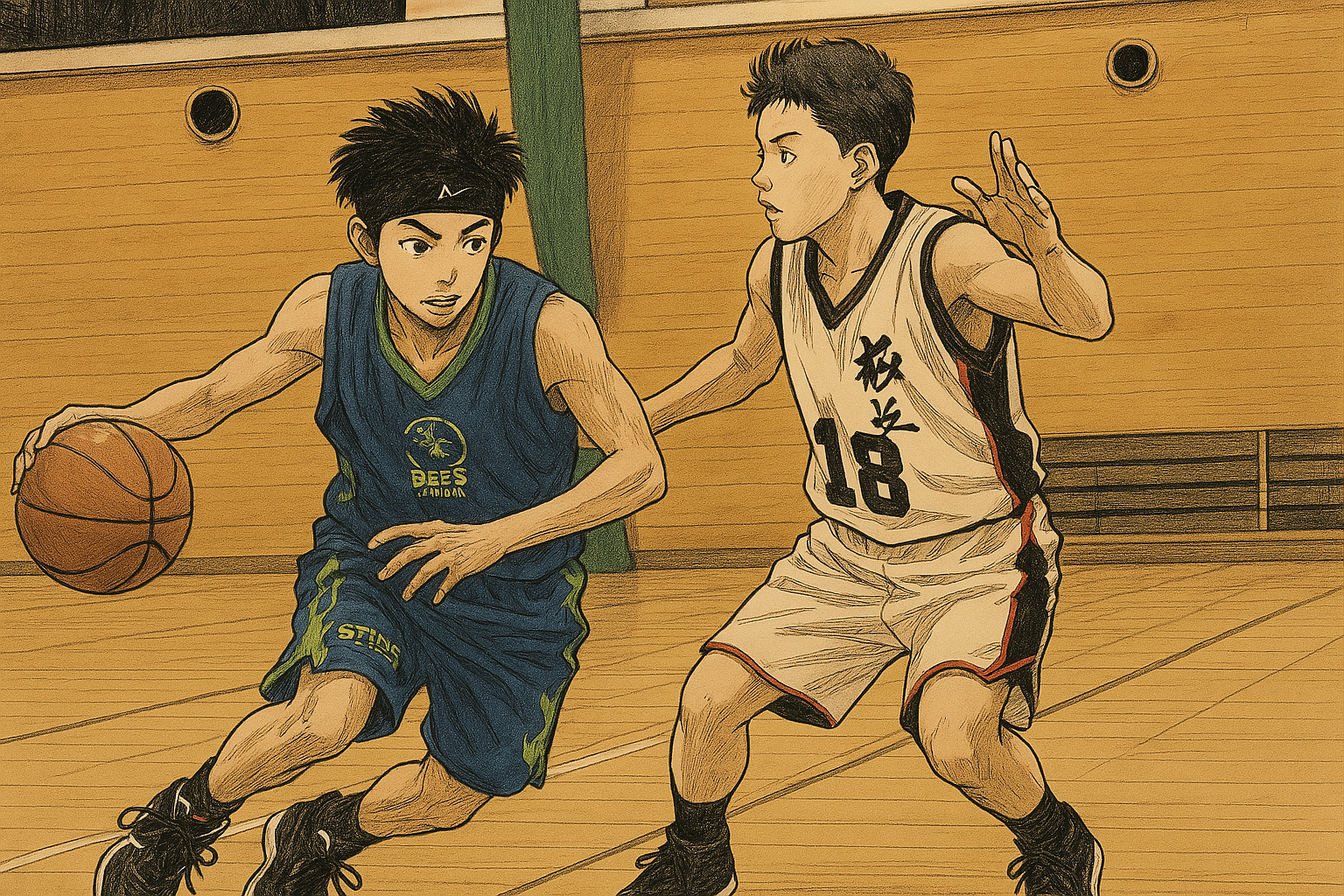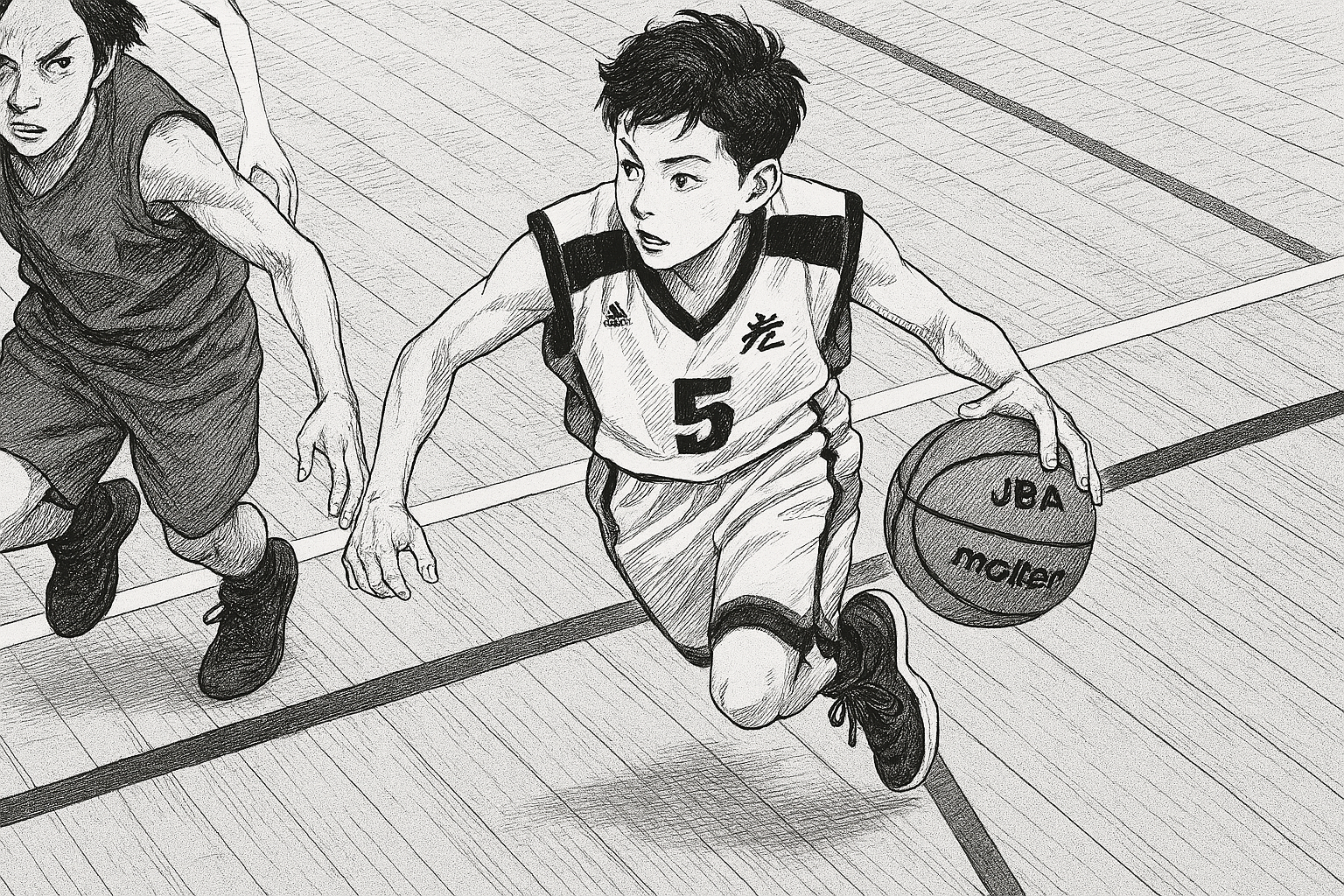みなさん、バスケットボールをプレーする上で「左利きって有利なの?」と疑問に思ったことはありませんか? 野球やテニス、サッカーのように「左利きが有利」とよく言われるスポーツもありますが、バスケだとどうなんでしょう。実はバスケットボールの世界でも、左利き(サウスポー)ならではの強みが議論されています。そこで今回は、欧米の研究やプロ選手の事例を踏まえつつ、左利き選手の戦術的メリットや育成環境などを幅広く掘り下げてみました。
左利き選手がもたらす戦術的インパクト
まず押さえておきたいのは、「他の競技と同様、バスケでも左利き特有の優位性はある」という点です。というのも、左利きの人口比率は全体の9~11%ほどと少ないため、相手が慣れていないことが多いのです。ディフェンダーの多くが右利き基準で攻守を組み立てるため、左利き選手の動きにはいつものリズムや感覚が通用しにくくなるのだとか。
たとえばシュートにおいては、右利きの守備者は無意識のうちに右手側をブロックしようとするため、左から放たれるシュートを止めにくくなると言われています。またドリブル突破やレイアップのシーンでも、ディフェンスは相手を左方向に追いやる傾向があるため、左利きにとってはむしろ得意なコースに誘導される結果になりがち。こうした「慣れの盲点」を突けるのは左利きならではの武器ですね。
もっとも、シュート成功率などの主要スタッツを右利きと比べた際には、必ずしも明確な差があるわけではないようです。NBAの2021-22シーズンで500分以上出場した選手を対象に調べたところ、左利きと右利きでのフィールドゴール成功率(FG%)はどちらも46.3%で同じ。3ポイント成功率に関しても左利き34.3% vs. 右利き35.7%と、ほぼ誤差レベルでした。トップレベルでは選手もディフェンスも対策をしっかりしているので、左利きだからといって成績が飛び抜けるわけではない、ということなのでしょう。
それでも、ユーロリーグで活躍するキース・ラングフォードなどの左利きの選手たちは「自分たちの動きに相手が慣れていない」ことを大いに利用して結果を出していると語っており、注意を怠ると右利きディフェンダーは翻弄されてしまうようです。最終的に高いレベルでは「左右両方の手を使えるかどうか」で真価が問われる、というのもバスケらしい奥深さと言えます。
NBAやユースでの左利き選手の割合とスターたち
次に、プロリーグやユースでの左利き選手の割合を見てみましょう。昔の研究(1946~2009年にかけてのプロ選手3,647人を対象)では、左利きは全体の5.1%しかおらず、一般人口における左利き比率(約11%)を下回っていました。ところが、その少数派の左利き選手たちは平均得点やリバウンド、ブロック数などで右利きよりも良い成績を残し、キャリアが長い傾向も確認されたそうです。
一方、近年はNBAの左利き選手の割合が10%前後に増えてきており、2021-22シーズンではローテーション入りしている選手374人中33人(8.8%)が左利きだったとのことです。過去の統計を合計すると記録上342人ほどの左利き選手がNBAに存在してきたそうで、現在は1チームに1人以上はいるケースも珍しくないんですよね。
そして、名選手の中にも左利きは多数。伝説のビル・ラッセル(11回優勝)や、元得点王・MVP経験者のデビッド・ロビンソンなどが代表格として挙げられます。ここ数年ではジェームズ・ハーデンやマヌ・ジノビリ、クリス・ボッシュといった選手が左利き勢の顔役を務めてきました。面白いエピソードとしては、レブロン・ジェームズやラッセル・ウェストブルックのように、普段は左利きだけどシュートは右手で打つというタイプもいること。逆に、右利きだけれど左手でも巧みにフィニッシュできる選手も多く、「この選手、どっちが利き手なんだろう?」と不思議に思う場面があるのもバスケの魅力ですよね。
左利き選手の育成と指導:欧米の取り組み
さて、欧米の育成環境では「左利きだけ特別待遇」というよりも、基本的には「両手をバランス良く鍛える」方向性が重視されています。たとえば、幼少期から左右どちらの手でもレイアップやパスができるように指導するケースが多く、実際にレブロン・ジェームズは子どもの頃、左手レイアップを延々と練習させられたという逸話が残っています。そのおかげで実戦でも自由自在に左右の手を使い分けられるようになったわけです。
イタリアの研究(2019年)では、プロのバスケ選手は日常生活では右利きが主流でも、競技中は左手を積極的に使う「セミ両利き」状態に近づくケースが多いと報告されています。特にポジションがポイントガードの選手だと、右手と左手をほぼ同等に扱えるようになることも。欧米のトップレベルでは「利き手の差をいかに小さくするか」が指導の鍵なんでしょうね。
とはいえ、ユース年代ではまだまだ右利き前提の練習メニューが多いのも事実。ある米国のコーチは「意図せず左利きの子どもにストレスを与えている」ことを警戒していて、練習で右手ばかりを使うよう指示すると、左利きの子どもが混乱して上達を阻まれる可能性があると指摘していました。こうした指導の現場を見直しながら、左利きにも両利きにもフレキシブルに対応できる環境を整備することが大事なんですね。
実際、20世紀の中頃までは「左利きを右利きに矯正する」文化が根強かった国もあり、スポーツの世界でも少なからぬ影響があったと言われます。しかし今ではその偏見が薄れ、「左利きはむしろ貴重な戦力」として歓迎される時代になりました。チーム戦術の幅を広げるために左利きの選手を何人か入れる、といった取り組みも進んでおり、NBAやユーロリーグで活躍する左利きプレーヤーが増えているのは、そうした育成環境の変化を反映しているのでしょう。
まとめ:左利きの希少性をどう活かすか
振り返ると、バスケットボールにおいて左利きは確かに「相手が慣れていない」という面でアドバンテージを持ちやすいようです。右利きだらけの環境で培われたディフェンスの常識を逆手に取れるわけですね。歴代のNBA選手を見ると左利きの人口比は少なかったものの、彼らは高いパフォーマンスを出して長く活躍してきました。現在では割合も10%前後と、一般人口とほぼ同じくらいにまで増えているのは興味深い傾向です。
ただし、プロレベルになると利き手のハンディキャップはかなり薄れてしまうため、最終的には「どこまで両手を使ってプレーを組み立てられるか」が勝負を分けます。そうした中でも、左利き特有のリズムを崩す動きは依然として相手にとって脅威ですし、育成年代にはコーチが左利きへの指導をきめ細かく行うことで、そのポテンシャルをより発揮させることができます。
「左利き=貴重な存在」という風潮が広まると、才能あるサウスポーがどんどん開花していきそうですね。もしあなたのチームにも左利き選手がいるなら、その独特の感覚を大切にしながら、右利きの常識に囚われないバスケを追求してみてはいかがでしょうか。
参考文献・情報源
本文中に登場した文献・データベース(研究論文や統計サイト、コーチや選手へのインタビューなど)を主に参照しました。
以上、左利き選手の優位性や育成環境について、欧米のデータや事例をもとにお伝えしました。左利きの方も右利きの方も、ぜひこの知見を参考にバスケを楽しんでみてくださいね!