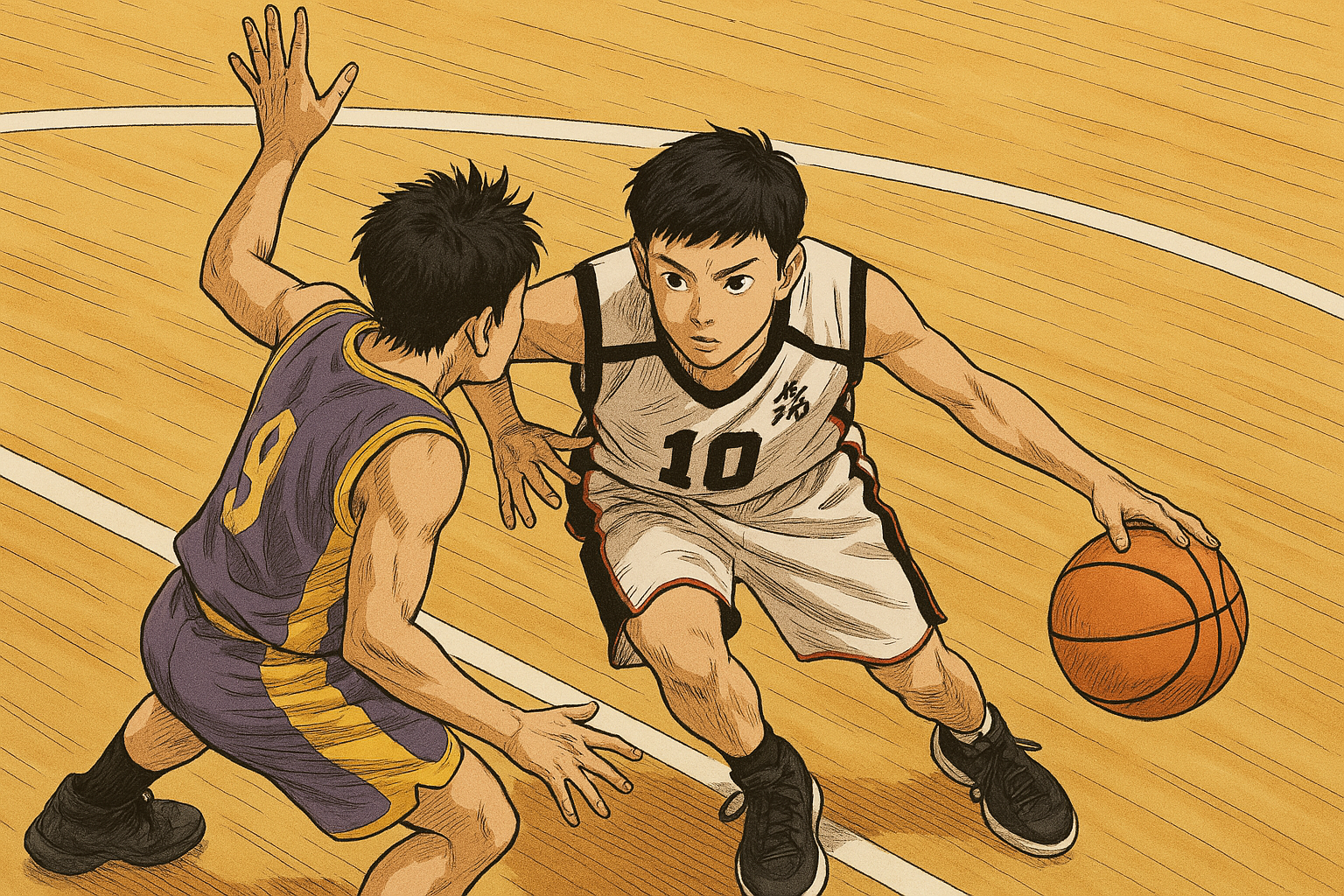こんにちは!今回は「ビデオゲームとスポーツパフォーマンスの関係」について、科学的研究をもとにいろいろと整理してみたいと思います。最近はeスポーツの盛り上がりもあって、ゲームとスポーツの関係性がますます注目を集めていますよね。実際、多くのアスリートがゲームを趣味にしているのも事実。では、ビデオゲームはスポーツパフォーマンスにどんな影響を与えるのでしょうか?短期的には反応速度や注意力などの向上が期待される一方、ゲームのやりすぎやタイミング次第では、逆にパフォーマンスが落ちる可能性も。そこで今回は、短期的・長期的に見た「ゲームとスポーツパフォーマンスの相関関係」を、科学的エビデンスに基づいて詳しく探ってみましょう。
はじめに
皆さんは「ゲーマー」と「アスリート」、どちらもイメージできますか?一見すると正反対の存在に思えますが、実は競技者の中にもゲーム好きは少なくありません。最近では、ビデオゲームがスポーツ選手の反応速度や注意力といった認知スキル、さらに試合での意思決定やトレーニングの成果に影響を与える可能性がいくつも報告されています。短期的・長期的な観点から、そのメリットとデメリットを整理しながら、代表的な研究結果を比較する表もご紹介します。ぜひ最後までご覧ください!
短期的効果:認知・運動スキルへの影響
まずは「短期的にどんな影響があるの?」という点です。とりわけアクションゲームやスポーツゲームのように、素早い反応が求められるジャンルは、実際の競技にも通じる認知スキルを養う可能性があると言われています。いくつかのポイントを見てみましょう。
- 反応速度の向上素早い操作を要求するアクションゲームを遊んでいると、視覚刺激に対する反応が速くなるという報告が数多くあります。たとえばゲーマーは非ゲーマーに比べて、「見たものへの反応速度」が高いと示す研究が存在します。2020年の研究(Reynaldo & Christian)でも、ゲーム経験がある人のほうが刺激に素早く応答できると報告されており、実際のスポーツでも打撃やゴールキーパーの反応などにプラスに働くかもしれない、とのことです。
- 視覚的注意・周辺視野の強化アクションゲームは多数の対象を同時に追いかけたり、画面をキビキビと見回したりするため、視覚的注意力が鍛えられると考えられています。研究では、ゲーム経験者は視野内の標識をより速く正確に認識し、多くの標識を見つけられたといった成果も報告済み。こうした「広い視野を確保する力」は、サッカーやバスケットなどで相手や仲間の位置を把握する際にも大きな武器になります。また、外科医を対象とした興味深い研究で、ゲーム経験のある外科医は腹腔鏡手術をより速く正確に行えたという例もあるそうです。
- 手眼協調と追跡能力シューティングゲームなどをプレイしていると、高度な「手と目の連動」が求められます。トロント大学の研究によると、ゲーマーは非ゲーマーに比べて「高速で動く物体を視線で追いかけ続ける能力」が優れていたとのこと。これは、ボールや対戦相手の動きを注視しながら適切に体を動かす必要があるスポーツシーンとも相性が良さそうですよね。
- 注意力・マルチタスク能力ゲームの世界では「マップを確認しながら敵を倒す」「複数の味方の位置をチェックする」など、同時に複数のタスクをこなします。2024年の研究では、アクションゲームを習慣的にプレイしている人は、非ゲーマーより空間的ワーキングメモリと複雑な注意力が高い成績を示したそうです。ただし単純な注意課題では差がなかったとのこと。つまり、空間把握やマルチタスクといった「より複雑な認知領域」でゲーム経験が役立つかもしれないというわけです。これは試合中の瞬間判断や次のプレーの選択にもつながりそうです。
こうした研究は「ゲーム経験者は認知・知覚能力が高い場合がある」と示唆しています。Green & Bavelierら(2012年)の古典的研究によると、アクションゲームによって新しい環境への順応力が増し、変化に直面しても集中力を維持できるとのこと。要するに短期的な認知のメリットがスポーツシーンにも波及する可能性は十分にあるわけです。ただし、後述するように短期的な悪影響もある点には注意が必要です。
短期的悪影響:試合直前のプレイや睡眠への影響
一方で、どんなときでもゲームが良いとは限りません。特に「試合前のゲーム」や「夜遅くまでのゲーム」は、スポーツパフォーマンスにとってマイナスになり得るという警告も出ています。
- 直前のプレイによるメンタル疲労試合前や練習直前のゲームは控えたほうがいいという考え方があります。イギリスオリンピック委員会のスポーツ科学責任者マルコ・カルディナーレ博士は「競技前のゲームはパフォーマンスに有害な可能性がある」と指摘し、特に睡眠の質低下を懸念しています。ブラジルのプロサッカー選手25名を対象とした研究(Fortesら2020)では、試合前にサッカーゲームやSNSをすると、その後の模擬試合でパスの意思決定精度が下がったと報告されています。バスケットボールでの類似研究(Faroら2022)でも同じような結果が出ており、ゲームによる認知的疲労が原因の一つになっている可能性が高いとのことです。大会前日や試合直前に、集中力の源をゲームに使い果たしてしまうのはリスキーかもしれません。
- 睡眠への悪影響ゲームをやりすぎると、寝る時間が削られてしまうことがありますよね。夜遅くまでプレイしていると、睡眠不足や睡眠の質の低下が起きやすいとされています。睡眠不足は反応時間の遅延や判断ミスの増加、さらには持久力低下にもつながるため、アスリートにとっては大問題。特に試合前夜や連戦が続く時期は、体調管理のためにもゲームを控えめにして早めに休むことが大切ですね。
まとめると、ゲーム自体を悪者にする必要はありませんが、プレイする「タイミング」と「時間管理」を誤るとスポーツパフォーマンスを落とすリスクがあるということ。せっかくゲームで認知的メリットを得ても、競技直前や深夜プレイで台無しにしてしまう可能性があるわけです。何事も“ほどほど”が大切ですね。
長期的効果:試合パフォーマンス・トレーニングへの影響
ここからは、もっと長いスパンで見たビデオゲームの影響についてご紹介します。最近は「シリアスゲーム」と呼ばれる、アスリートの認知スキルを鍛えるためのトレーニング特化型ゲームも登場しており、実際の現場でも活用され始めています。
認知トレーニングとしてのゲーム活用とパフォーマンス向上
- 意思決定力・注意力の向上(サッカー選手)2024年に発表されたランダム化比較試験(Feria-Madueñoら)では、8~10歳の少年サッカー選手20名を対象に「注意力を高めるビデオゲーム」を6週間、週2回15分ずつ導入し、その成果を調べています。結果として、ゲーム訓練グループは対照群よりサッカーの意思決定能力が高まったとのこと。コーチによる評価やテスト結果でも有意な差が確認されました。時間やコストをあまりかけずに認知スキルを鍛えられるなら、アマチュアやジュニア世代にもありがたいですよね。
- 危機回避能力・認知処理の向上(アイスホッケー選手)アメリカのユース・アイスホッケー選手を対象にした研究(DiFabioら2021)では、「IntelliGym」というホッケー用の認知トレーニングゲームを週2回30分、20週間実践したグループが、頭部衝撃の回数や強度を大幅に減らしたという成果が得られています。対照群(試合映像視聴のみ)と比べて、シーズン後半での衝突が少なく、危険回避能力が向上したのではないかと推測されています。脳震盪リスクの低減や選手生命の延長にもつながり得る重要な効果ですよね。
- 統計上のパフォーマンス向上(バスケットボール選手)大学バスケットボール界でも、IntelliGymのバスケット版が導入されており、NCAAディビジョンIの強豪校でターンオーバーの減少やアシスト数の増加といった報告がされているそうです。学術論文というよりはコーチング現場での報告ベースですが、長期的なゲーム活用によるプラス効果が示されている興味深いケースです。
こうした事例から、ゲームを「トレーニングツール」として計画的に導入すれば、長期的には競技力の向上につながる可能性が十分ある、と言えそうです。従来のフィジカルトレーニングに加えて、脳や認知を鍛えるイメージですね。
習慣としてのゲームと身体活動のバランス
ただし、ゲーム習慣が長期的にスポーツ活動に悪影響を及ぼすケースもあります。たとえば「ゲームばかりやっていたせいで体を動かす時間が減り、競技力が下がる」というリスクです。
- 身体活動不足によるパフォーマンス低下リスク10~14歳の子どもを対象にした研究(Burnsら2022)では、普段から定期的に運動しているグループとゲーム中心の生活をしているグループを比べたところ、反応時間に大きな差がついたそうです(平均0.327秒 vs 0.403秒)。運動+ゲーム両方をほどほどにやっている子どもは中間的な値だったとのこと。やはり成長期には運動による神経系の発達が重要で、ゲームだけではカバーしきれない面があるのかもしれません。
- 心理・社会的影響アスリートは勝負や競争への意欲が強いので、ゲームに対しても「もっと勝ちたい」「もっと上手くなりたい」とのめり込みやすいと言われています。その結果、ゲーム依存(Gaming Disorder)になるリスクが高まる可能性もあるようです。世界保健機関(WHO)や米国精神医学会もこの問題を指摘しており、過度なゲームプレイで睡眠不足や練習不足、人間関係のトラブルが起きれば当然競技パフォーマンスにもマイナスですよね。
- スポーツ知識・戦術理解への貢献逆にポジティブな面として、野球ゲームやサッカーゲームなどを通じてルールや戦術を学び、現実のプレーに生かす選手もいるようです。実際、ある調査では「21歳未満の男性ゲーマーの38%が、自分のやっているスポーツと同じ種目のゲームを遊んでいる」というデータがありました。NBA2Kでバスケット戦術を試してみたり、FIFAでサッカーのフォーメーションを考えたりと、楽しみながら戦略的思考を育めることが期待されます。ただし「ゲーム内の戦略がそのままリアルの試合で通用するわけではない」という点は頭に入れておきたいですね。
主な研究結果の比較
ここまでの内容を、短期的な研究と長期的な介入研究に分けて表にしてみました。ゲームとスポーツの相関関係をどう捉えているか、一目でわかるように並べてあります。
| 研究(年) | 対象(競技レベル) | ビデオゲーム条件・介入 | 評価したパフォーマンス | 主な結果 |
|---|---|---|---|---|
| Fortesら (2020) | プロサッカー選手25名 | 試合直前に以下を実施: ①コントロール(何もしない) ②スマホでSNS閲覧 ③サッカーゲームをプレイ |
模擬試合でのパス意思決定の正確性 | スマホ条件およびゲーム条件で、パス判断精度が有意に低下。ビデオゲーム直後は意思決定力が落ちる(メンタル疲労の影響)。 |
| Faroら (2022) | 男子バスケット選手20名 | (Fortes研究と類似)試合前にバスケットゲームを一定時間プレイさせ、対照と比較 | 視覚‐運動スキル(シュート精度や反応時間等) | ビデオゲーム後に視覚‐運動反応が低下し、メンタル疲労が原因と推定(国際スポーツ・エクササイズ心理学誌, 2022年)。 |
| Burnsら (2022) | 子供67名(一般; 10~14歳) | 普段の習慣による3群: ①定期的に運動 ②主にビデオゲーム ③両方を同程度 |
コンピュータによる視覚刺激への反応時間 | 運動習慣のみの子供がゲーム習慣のみの子供より有意に反応が速い (0.327秒 vs 0.403秒)。両方群(0.386秒)は中間値で、有意差なし。 |
| Feria-Madueñoら (2024) | 少年サッカー選手20名(平均8.5歳) | 6週間の訓練: ①通常練習+注意力向上ゲーム(週2回×15分) ②通常練習のみ |
サッカーの意思決定力(特定場面での判断テスト) | ゲーム訓練群で意思決定スコアが向上し、対照群との差が有意に。特に攻撃場面での判断質がアップ。コーチ評価も高評価に。 |
| DiFabioら (2021) | ユースアイスホッケー選手20名 | シーズン中の介入: ①通常練習+IntelliGym認知ゲーム(週2回×30分を20週間) ②通常練習+ホッケー試合映像の視聴(対照) |
頭部衝撃の頻度と強度(加速度) | ゲーム訓練群はシーズン後半に頭部衝撃回数が大幅に減り、累積加速度も低下。対照群では変化なし。認知トレーニングにより危機回避能力が上がった可能性。 |
| Campbellら (2024) | 成人ゲーマー36名 vs 非ゲーマー30名(一般) | 認知疲労課題(長時間の注意課題)前後での認知テスト比較 | 認知機能(注意力・ワーキングメモリ等) | ゲーマーは非ゲーマーより空間ワーキングメモリと複雑な注意力が高い。一方、疲労後のパフォーマンス低下率は両者同程度。ゲーマーが疲労に強いわけではないとのこと。 |
このように、短期的には「試合直前のゲームが意思決定精度を下げる」「運動習慣が足りないとゲームで得られる反応速度向上効果よりむしろパフォーマンスが落ちる」といったリスクが明らかになっています(Fortesら2020、Faroら2022、Burnsら2022)。一方で、長期的に見ると適切な介入型ゲーム(Feria-Madueñoら2024、DiFabioら2021)で認知スキルが上がることも示唆されており、さらにゲーマーの高い認知スキルを証明する研究(Campbellら2024)も存在します。ただし、過信は禁物で、誰でも疲れは溜まるというのが現実のようです。
結論
今回のテーマ「ビデオゲームとスポーツパフォーマンス」については、科学的見地からポジティブ面・ネガティブ面の両方が浮き彫りになってきました。アクション性の高いゲームは反応速度や注意配分などを強化する可能性があり、うまく利用すれば競技力向上の助けになることもわかっています。しかし、試合直前のプレイや夜更かしプレイによる睡眠不足は、短期的に大きなマイナスをもたらし得るという研究が同時に存在するんですね。さらに、長期的には“ゲームを使ったトレーニング”で意思決定や危険回避を伸ばせる一方で、ゲームに偏りすぎて運動量が足りなくなったり、依存症リスクを高めたりするとパフォーマンスを損なう可能性もある。
結局のところ「使い方次第」だという結論に落ち着きそうです。ゲームを利用した認知トレーニングは今後さらに盛んになると予想されますが、選手個人やチームとしては、ゲームの種類やプレイ時間、タイミングを上手にコントロールしないと逆効果になるかもしれません。今回ご紹介した研究結果も踏まえながら、「いかにバランスを取るか」がこれからの課題でしょう。今後は、より洗練されたゲーム活用方法が確立されていくことが期待され、その際にはここで取り上げたような科学的根拠が重要な指針となりそうです。
参考文献
本稿で引用した内容は、科学ジャーナル論文や学術レビュー、および関連研究の要約などを参考にしています。各段落末の引用番号は、該当する研究やレビューの文献リストを示すものです。興味を持たれた方は、ぜひ元論文にもあたってみてくださいね。