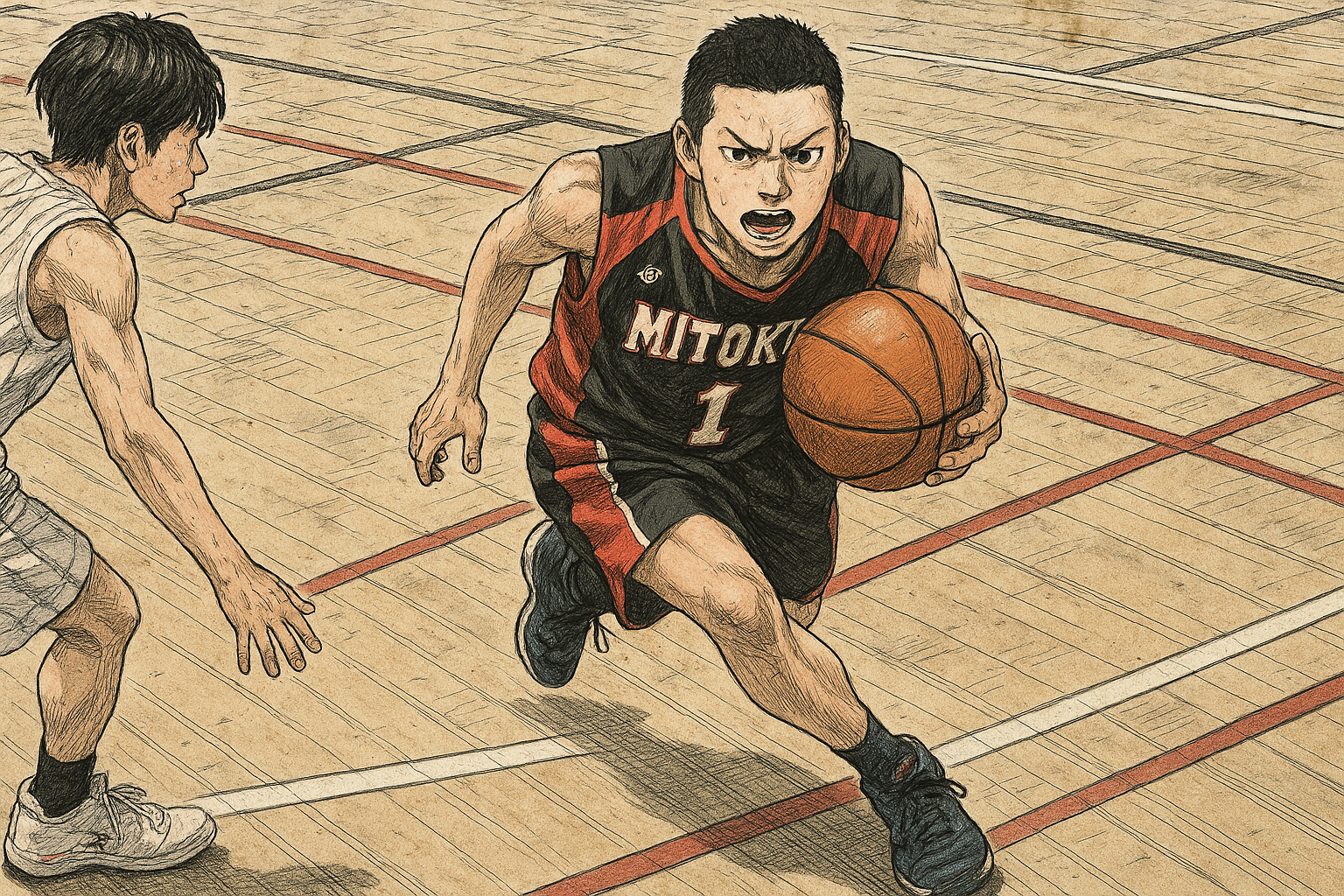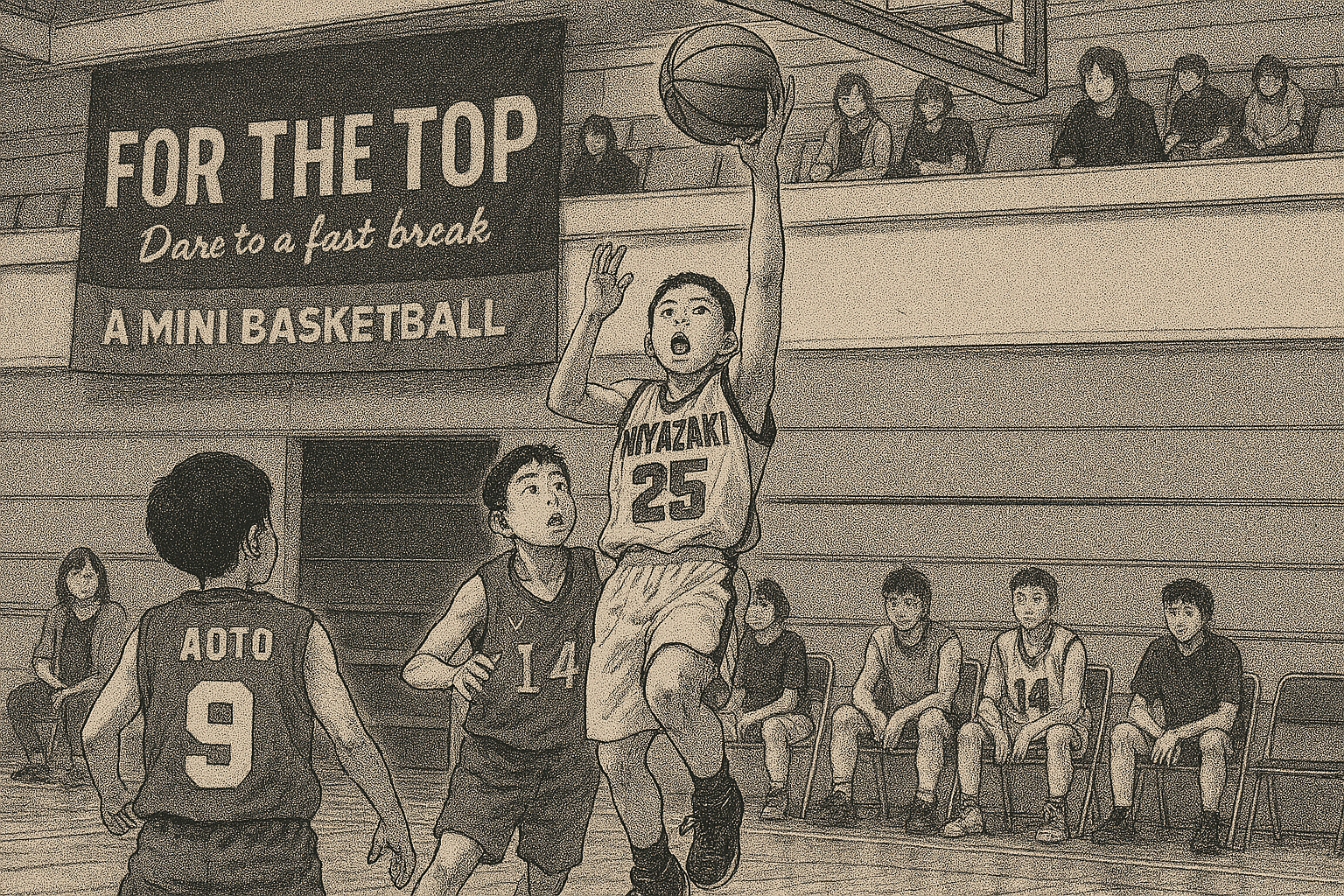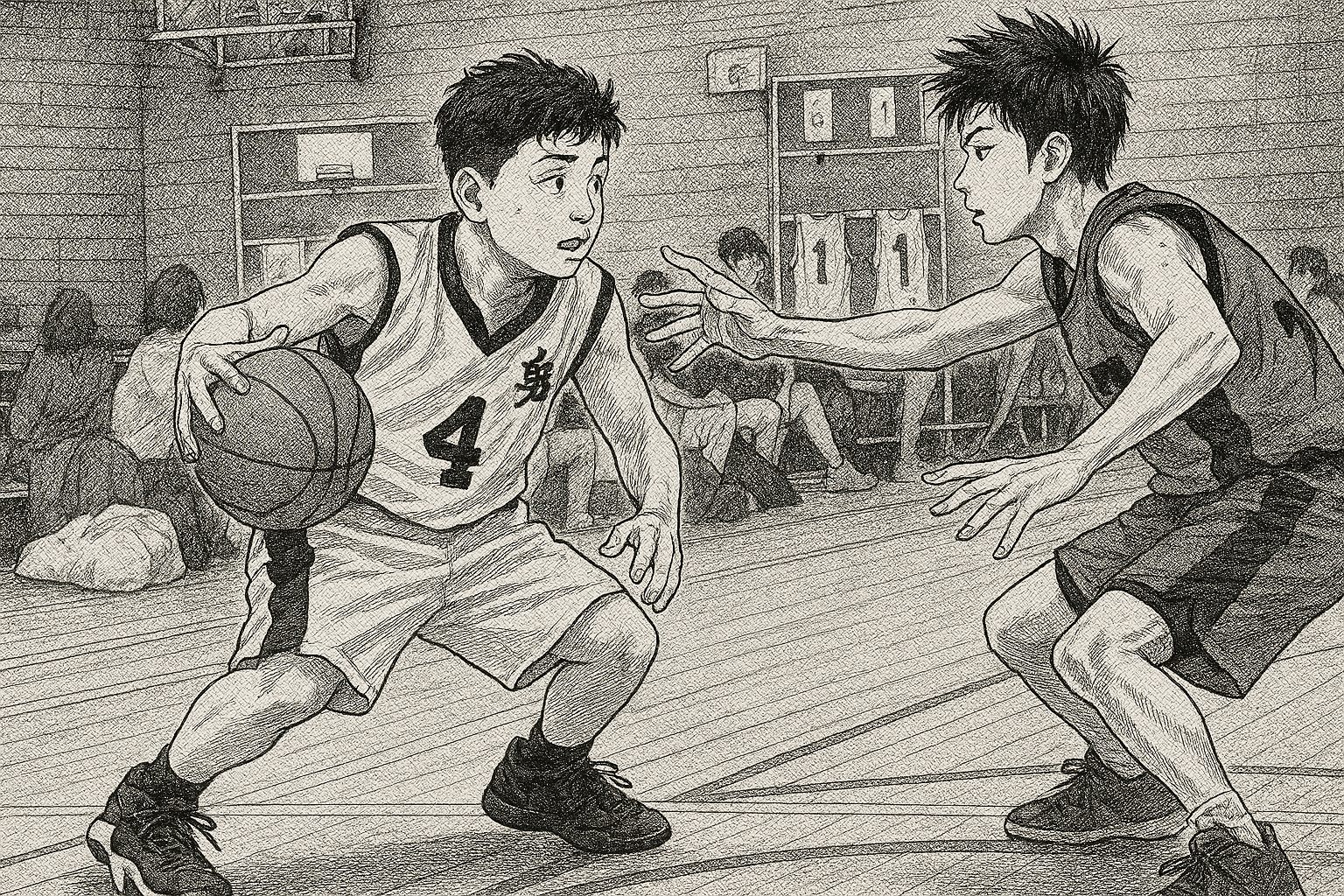子どもの頃に運動能力や体力が低かった人でも、思春期から青年期(10代〜20代)にかけて大きく成長する可能性があります。その背景には、遺伝的な素質と環境要因の両方が関係しており、特に思春期の身体発達や適切なトレーニングは体力・運動能力を飛躍的に向上させることが知られています。本記事では、遺伝要因と環境要因の影響、トレーニングや生活習慣の役割、バスケットボールを例としたスポーツにおける成長可能性、さらには筋力・持久力・柔軟性といった他の運動能力の変化について、10代〜20代を中心に詳しく見ていきます。
遺伝的要因と環境的要因の影響
運動能力や体力は、遺伝要因と環境要因の両方から影響を受ける複合形質です。双子や家族を対象とした研究では、筋力や持久力、高さ(身長)、柔軟性など運動能力に関連する特徴の個人差のうち、約30〜80%ほどが遺伝的要因で説明できると報告されています。たとえば筋肉のタイプ(速筋繊維・遅筋繊維の割合)や身長は遺伝の影響が大きい要素であり、これらが運動能力の土台となりやすいのです。
一方で、残りの20〜70%程度は育った環境や本人の経験によって左右されます。具体的には、家族や指導者によるサポート、経済的な環境、スポーツに触れる機会、さらには同級生との相対的な年齢差といった要因が大きく作用するのです。遺伝要因と環境要因は相互作用を起こすため、幼少期に身体能力が低かった場合でも、体質(遺伝的影響)だけでなく、幼少期の遊び方や生活習慣(環境面)もしっかり考える必要があります。
さらに重要なのは、「遺伝的に不利な要素を持っているかもしれない」という場合でも、適切な環境次第で大きく能力を伸ばせるという点です。たとえば、最大酸素摂取量や筋力といった遺伝の影響が強い指標でも、トレーニングや栄養が整えば顕著に改善できることがわかっています。実際、一卵性双生児でも運動経験が異なると体力テストで差が生じる事例があるなど、後天的な要素の力は決して小さくありません。つまり子どもの頃に身体能力が低くても、それが未来の運動能力を一律に決定づけるわけではなく、周囲のサポートや本人の努力によっていくらでも変化が可能ということです。
トレーニングや生活習慣の影響
環境要因のなかで特に大きなウェイトを占めるのが、トレーニング(訓練)と生活習慣です。子ども時代に体力が劣っていた人であっても、10代以降に正しい運動習慣を身につければ大きな追い上げが可能だとされています。実際、子ども〜青年期における抵抗運動(筋力トレーニング)は筋力や運動パフォーマンスを有意に向上させることが、多くの研究レビューで示されています。成長期の青少年に筋力トレーニングを行った介入研究のまとめでは、筋力が特に大きく上がり、走・跳・投などの運動能力にも小〜中程度の改善がみられたという結果が示唆されています。
さらに、安全面で懸念があった「子どもの筋力トレーニング」も、最近では「適切な方法で行うのであればむしろ健康や体力向上に有益」という意見が主流です。筋トレに対する理解が進むことで、若年層におけるトレーニングの選択肢が増え、その後の成長にプラスの影響を与えています。
また、生活習慣そのもの—日頃の身体活動量や栄養、睡眠など—も長期的に体力を左右します。幼少期にほとんど運動をしてこなかった場合、そのままだと青年期・成人期になっても運動不足に陥りがちです。実際、10〜11歳時点と15〜18歳時点の体力テスト結果を追跡し、23〜25歳頃になったときの運動習慣と比較する研究では、子ども時代に持久走や腹筋テストの成績が低かった男子が「成人後に運動不足になる確率が高い」という傾向が示されています。
しかし、同じ研究で興味深いのは、親や周囲の運動に対する励まし、高校卒業後のスポーツへの参加など「環境要因」がその後の運動習慣を好転させる力を持っていたことです。つまり子どもの頃に低かった体力も、家族や学校の支援、運動機会の提供などがあれば若い時期に活発に体を動かす習慣を得やすくなるというわけです。
そして、成長期に欠かせない睡眠や栄養も非常に重要な要素となります。タンパク質やミネラルを含むバランスの良い食事は筋肉や骨の発達に役立ち、成長ホルモンの分泌は主に睡眠中に起こるため睡眠不足は成長を妨げる要因になります。逆に、テレビやゲームの時間を減らしたり、ジャンクフードを控えて良質な栄養をしっかり摂るようにしたりすることで、遺伝的な限界に近いレベルまで身体能力を伸ばすことが可能になるのです。つまり、「幼少期に低かった体力は、思春期以降に適切なトレーニングと良好な生活習慣を取り入れることで大きく向上できる」というのが、多くの研究で示される一致した見解といえます。
思春期の身体発達と運動能力の変化
思春期は身体能力が大きく伸びる時期で、子どもの頃の遅れを取り戻すチャンスとも言われます。男子では12〜15歳、女子では10〜13歳頃から第二次性徴が始まり、身長・体重の増加だけでなく筋力や持久力といった体力面でも著しい伸びが見込めるのが特徴です。
- 身長と体格の急伸思春期には「成長スパート(思春期スパート)」と呼ばれる急激な身長の伸びがあり、男子なら平均14歳前後、女子なら12歳前後がそのピークとされています。男子は年間7〜12cm、女子は6〜10.5cm程度伸びるのが一般的で、体重も男子では6〜12kg、女子で5.5〜10kgほど増えることがあります。この時期に骨格や筋肉量が一気に増え、大人の体格にグッと近づいていきます。
- 筋力の発達男子は思春期に入ると男性ホルモン(テストステロンなど)の分泌が増え、筋肉が急激に発達します。13歳頃から筋力アップのペースが加速し、筋肉量のピーク増加から約1年後に筋力の最大発達が訪れるという研究結果もあります。女子も同様に筋力が伸びますが、15歳前後で伸びがやや鈍化する傾向があります。それでも、思春期全般で見ると筋力・スピード・パワーといった要素はどの年齢期よりも著しく伸びると言われ、男子では腕立て伏せや懸垂などのスコアが14〜18歳の間に飛躍的に高まる例が多いです。さらに、この時期に適切な筋力トレーニングを取り入れると、通常の自然成長以上に筋力を増強できる可能性も示されています。
- 持久力・心肺機能の発達思春期には心臓や肺の機能も大きく発達し、全身持久力(心肺持久力)が向上します。特に男子の場合は血液量やヘモグロビン濃度が大幅に上がり、最大酸素摂取量(VO₂max)も顕著にアップすることで持久力が飛躍的に向上しやすいのです。中学・高校時代の陸上長距離選手が、短期間でタイムを大きく伸ばすケースはこれに起因すると考えられます。女子も同様に伸びはありますが、男子ほど顕著ではない傾向が一般的といわれています。いずれにしても多くの人は18〜20歳頃に筋力や持久力のピークを迎え、ここで培った体力がその後の人生の土台になると指摘されることも少なくありません。
- 柔軟性と調整力女子の方が一般的に柔軟性は高く、男子は急激な成長のタイミングで一時的に体が硬くなることがあります。骨格が急成長するぶん筋や腱の伸びが追いつかず、柔軟性が低下し「成長期の不器用さ」が出る場合もありますが、これは一時的な現象であり、体が新しい大きさに慣れてくると再び運動の巧みさは回復します。思春期特有のぎこちなさを理解し、子どもを励ましてあげることが大切です。
このように、思春期という時期は子どもの頃に低かった体力や運動能力を底上げする好機といえます。全国の体力測定結果を見ても、中学生から高校生の間で多くの種目の平均記録が上昇し、18〜20歳でピークを迎えるというパターンがはっきり示されています。ここでピークをできるだけ高いレベルに持っていくかどうかが、その後の体力レベルを大きく左右するのです。
早熟型と晩熟型:成熟のタイミング差
同じ思春期でも、成長が早い「早熟型」とゆっくりな「晩熟型」があり、差はかなり大きい場合があります。たとえば15歳前後の男子では、早熟型のほうが背も高く、体重も重く、スプリント能力や試合中の走行距離も優れているという研究があります。遅れて成熟する晩熟型は、一時的に体格や筋力で見劣りするため、中学や高校の部活動などでは不利に感じることもあるでしょう。
しかし「晩熟だから将来も不利」というわけではなく、その後の急成長で同世代を追い越すケースは多々あります。実際には「小柄で非力だった時期に磨かれたテクニックや戦術理解が、体格が追いついた瞬間に爆発的に活きる」という現象がしばしば報告されており、これを「Late bloomer(遅咲き)」と呼ぶこともあります。専門家は子どもの頃の体格や運動能力だけで才能を断定しないように警鐘を鳴らしているのです。
晩熟型のメリットとしては、小さい頃から身体能力に頼らず技術や判断力で勝負せざるを得ない状況が、結果的に高いスキルや戦術眼を育むという点です。バスケットボールやサッカーなどの競技では、成長期に体格で劣る選手ほどドリブルやパスなどの技術を高めるため、思春期後期に身長や筋力が追いついたときに一気にブレイクする可能性があります。つまり、子どもの時点で大きく差があるように見えても、20代になるまでに逆転が起こりうる世界なのです。
バスケットボールにおける成長の可能性
子どもの頃に運動能力が低かった人が、たとえばバスケットボールで活躍するようになる可能性について考えてみましょう。バスケは身長やジャンプ力など身体的要素が重視される反面、思春期の成長とトレーニングしだいで大きく伸びる余地がある代表的なスポーツのひとつです。
- 身長と体格面バスケットボールでは身長が高いと有利ですが、成長スパートのタイミングによっては中学時代に小柄だった選手が高校になって急激に伸びることは珍しくありません。男子なら高校生年代まで背が伸び続け、遅咲きの選手だと10cm以上急伸することもあるのです。プロのバスケットボール選手にも高校〜大学で身長が大きく伸びて才能を開花させた例が報告されており、子どもの頃の身長や体格だけで将来を判断するのは早計といえます。
- 身体能力(ジャンプ力・俊敏性など)走る速さやジャンプ力も、思春期の筋力・パワー発達で大きく変わります。小学生の頃に足が遅くても、高校生になる頃には筋力がついて走力が大幅に伸びるということも十分起こりえます。加えて、プライオメトリクス(瞬発系のトレーニング)などを10代で取り入れれば、神経系の発達がまだ柔軟なこの時期に、跳躍力やダッシュ力を飛躍的に向上させる可能性もあるのです。
- 技術・ゲームIQバスケは身体能力だけでなく、ボールハンドリングやシュートテクニック、戦術理解も欠かせません。幼少期に身体能力で劣っていた選手は、その間に技術面やゲームIQをより深める傾向があるといわれます。中学時代に体格で負けていた選手が高校で身長・筋力が追いついたとき、技術的にも頭一つ抜ける存在になれるかもしれません。実際、ユース期のバスケットボール選手を追跡した研究で、「12〜14歳時点の技術スコアが低めだった選手が思春期に大きく伸びる例」も確認されています。
- 早期専門化の是非バスケットボールで成果を出すために「幼少期からその競技一本に専念しなければならない」と考える人もいますが、研究によれば思春期前からバスケだけに絞っても、思春期以降の体力向上に大きなアドバンテージは得られないことが示唆されています。むしろ、いろいろなスポーツを経験し、楽しみながら多角的に基礎体力や運動スキルを高めておいた方が長期的にはプラスになる可能性が高いのです。事実、トップレベルのバスケ選手のなかにも、中学までは他競技と並行していて、高校から本格的にバスケに注力したケースは少なくありません。
要するに、バスケットボールのように身長・瞬発力が重要視される競技であっても、思春期〜20代前半にかけての成長やトレーニングしだいで劇的に変化できる潜在性が十分あるのです。子どもの頃の身体能力が平凡でも諦める必要はありません。
他のスポーツや運動能力の場合
バスケットボール以外のスポーツや筋力・持久力・柔軟性といった個別の運動能力も、10代〜20代にかけて大きく伸びます。
- 筋力・パワー系スポーツウエイトリフティングや投擲競技など、筋力がものを言う競技では思春期〜20代前半で記録が飛躍的に伸びるのが普通です。子どもの頃は非力でも、高校・大学年代で漸進的な筋トレを行えば、筋力が何倍にもなることがあります。男性は20歳前後で筋力がピークを迎えやすいため、10代のうちに適切なトレーニングを積むかどうかでピーク時のレベルが大きく変わるのです。
- 持久力系スポーツマラソンや自転車競技、長距離走では、心肺機能の成長が鍵になります。思春期に最大酸素摂取量を高めるトレーニングを行うと、10代後半〜20代でタイムが大幅に向上するケースが多く見られます。逆に思春期に運動習慣をまったく持たなかった人は、体力が伸び悩んだり早々に低下してしまう傾向が指摘されているため、若いうちからの継続的な持久系トレーニングが重要だといえます。
- 柔軟性遺伝的な関節の構造や筋腱の特性もありますが、ストレッチやヨガを続ければ可動域を広げることは可能です。男子は思春期の急成長で一時的に柔軟性が低下しやすいものの、地道なストレッチを積み重ねることで一般的なレベルを越える柔軟性を獲得できることもあります。ただし、成長期に無理をして開脚などをすると筋や腱を傷めるリスクがあるため、注意が必要です。
- 敏捷性・バランス能力敏捷性(アジリティ)は神経系の発達と密接に関係しているため、子どもの頃に「運動神経が悪い」と思っていても、適切なトレーニングで劇的に変わる可能性があります。ラダードリルや方向転換走などで瞬発力や反応速度を鍛えれば、10代〜20代での伸びが大きく期待できるでしょう。バランス能力もコアトレーニングなどで育成可能で、成長期に基礎的なバランス感覚を養うとケガ予防にもつながります。
総じて、筋力・持久力・柔軟性・敏捷性などの運動能力は10代〜20代に最も発達しやすく、適切な取り組みをすれば「子どもの頃の差を埋める」「逆転する」ことも大いにあり得るわけです。大学生年代(18〜22歳頃)は多くの体力指標が生涯でピークとなる時期でもあり、そのピークの高さを左右するのが思春期の過ごし方やトレーニングです。
まとめ
子どもの頃に体力や運動能力が低かった人であっても、10代〜20代にかけて大きく伸びる可能性について、遺伝・環境要因や思春期の身体発達などの視点から見てきました。たしかに遺伝の影響は大きいものの、環境次第で結果を大きく変えられるのが人間の体の特徴です。思春期は身長の伸長や筋力・持久力が自然に高まる時期であり、それをさらに伸ばすためのトレーニングや生活習慣の改善によって、子どもの頃には考えられなかったレベルのパフォーマンスに到達できる可能性が十分にあります。
実際、子どもの頃の体力と成人後の体力にはある程度の相関がある一方で、思春期〜20歳前後でどれだけ運動に取り組むかが将来の健康や体力を左右するという研究結果も多数報告されています。専門家たちは、「子どもの頃は体力が低めだった子でも、適切な時期の的確なサポートがあれば、その後の人生で大きく花開く」ことを強く訴えています。
「子どもの頃の低い体力は一生低いままではない」
このメッセージは多くの研究で裏付けられており、遺伝的な限界はもちろんありますが、思春期のうちに適切な環境とトレーニング機会を与えられれば、想像以上の伸びしろがあるのです。大切なのは、「幼少期に劣っていたからダメだ」と悲観するのではなく、長い目で見て思春期を中心とした若い時期に体をしっかり鍛え、運動を続けること。そうすれば、10代〜20代に驚くほどの成長を体感できるかもしれません。
参考文献・出典
本記事で述べた内容は、以下のような最新の研究論文や公的データに基づいています(遺伝と環境の影響 、幼少期体力と成人後の関連 、トレーニング効果 、思春期の身体発達 、早熟・晩熟の影響 、バスケットボールにおける研究 など)。これらの研究からは、「適切な時期に適切な働きかけを行うことが、将来の体力や運動能力を大きく左右する」という科学的エビデンスが示されています。
本記事が、思春期における体の変化やトレーニングの大切さ、そして子どもの頃に低かった体力がいかに伸びる可能性を秘めているかを理解するヒントになれば幸いです。もし周りに運動が苦手な子どもがいたり、自分自身が「昔は運動が苦手だった」という経験をお持ちなら、ぜひ思春期〜20代にかけての取り組みを前向きに考えてみてください。必ずや、未来を切り拓く大きな一歩となるはずです。