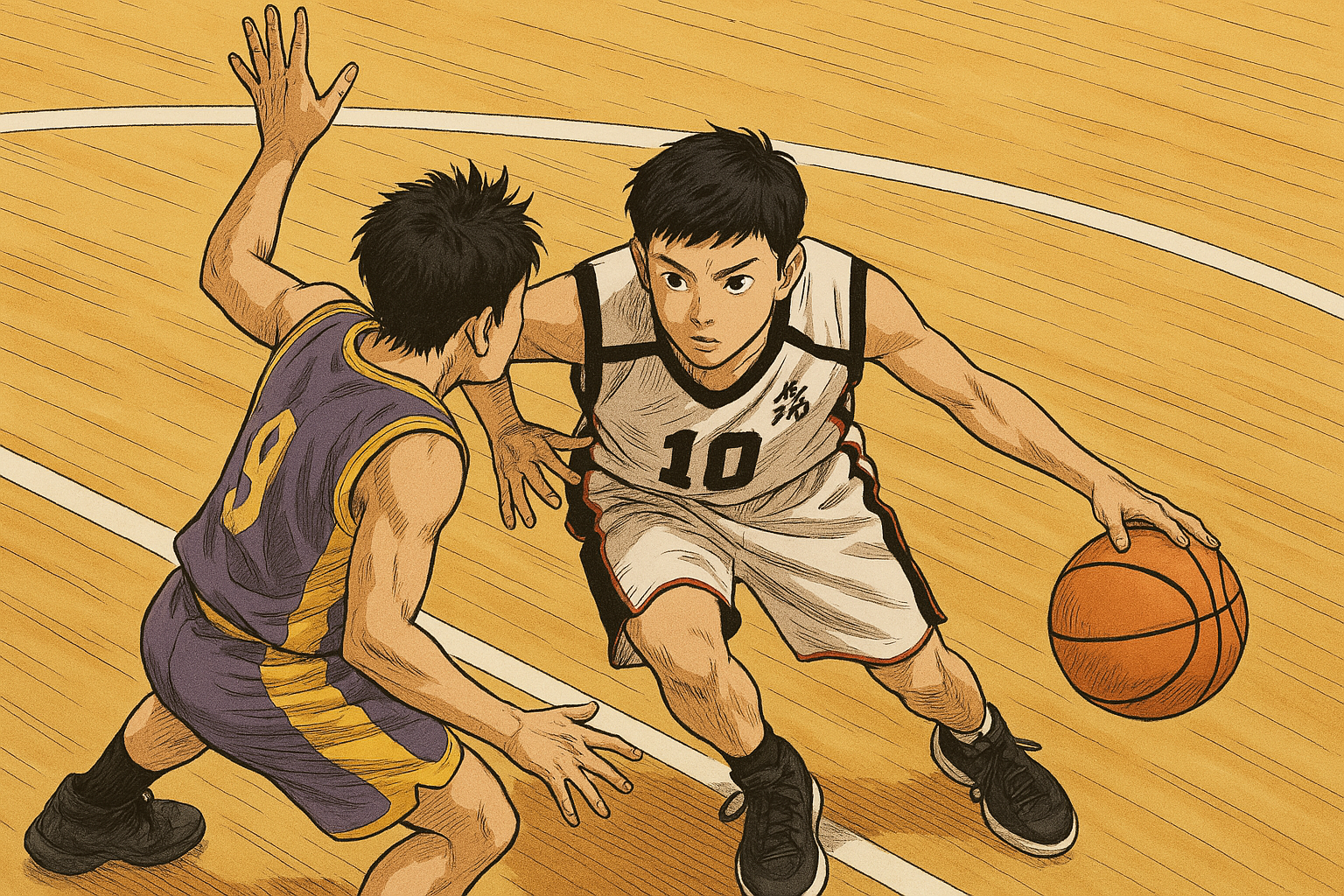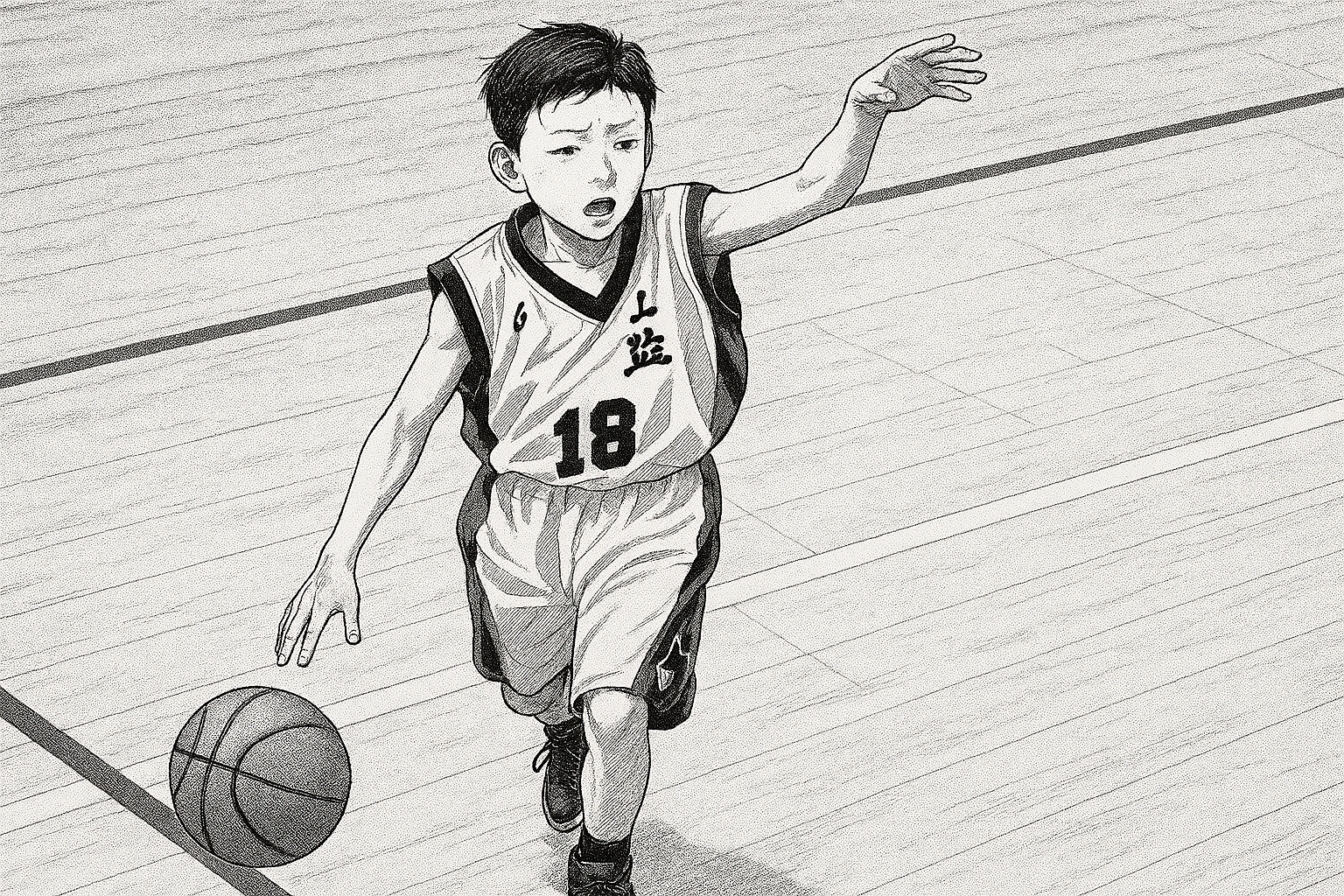こんにちは!今回は、6〜18歳のジュニア世代にスポットを当てて、スポーツ競技と近視の関係を紐解いてみたいと思います。世界的に子どもの近視が増えているというニュースは耳にしたことがある方も多いと思いますが、実は屋外スポーツか屋内スポーツかによって、近視リスクに違いがあるんです。そこで、本記事では最新の研究データや統計を踏まえつつ、どのようにスポーツ選びや屋外活動が視力に影響を与えるのか、具体的にご紹介していきます。
近視の発症リスクと屋外活動時間
まずは、子どもの近視が近年ますます大きな課題になっている背景から見てみましょう。東アジアをはじめ世界的に近視が急増しており、その原因として注目されているのが「屋外活動時間の不足」です。もちろん遺伝的な要因もありますが、研究では屋外活動が少ないと近視リスクが高まり、逆に屋外で過ごす時間が長いと近視発症を抑えられると報告されています 。米国のOrinda Longitudinal Study of Myopiaでも、小学生のときに週あたりのスポーツ・屋外活動が少なかった子どもたちのほうが、将来近視になる割合が高いという結果が示されています(将来近視群約8時間 vs 非近視群約12時間, p<0.001) 。
ここで注目したいのは、たとえ親が近視でも、子ども自身が屋外活動を積極的に行えば発症リスクが低下するという点です。いろいろな国で同様の研究結果が得られており、「外で遊ぶ(スポーツも含む)」というアクションが、いかに子どもの視力を守ってくれるかが分かります。
さらに興味深い研究として、オーストラリアとシンガポールの比較が挙げられます。どちらも同じ中国系の6〜7歳児を対象にした調査ですが、シンガポールの近視有病率は29.1%に対し、日照時間が長く屋外活動が盛んなシドニーではわずか3.3% という大きな差がありました 。その違いの一因として、シドニーの中国系児童の週平均屋外活動時間は13.8時間に対し、シンガポールではわずか3.1時間というデータがあるのです 。こうした屋外活動量の差が、遠視寄りの屈折(=近視が少ない方向)を維持してくれるか否かに関わっているようです。
メタ分析の報告では、屋外活動を1日あたり約76分増やすと近視になるリスクが約50%も減少するというデータも 。一方、スマートフォンやコンピュータなどスクリーンを見る時間の長さは近視リスクを押し上げる要因になります 。こうした一連のエビデンスから言えるのは、日中に太陽の下でスポーツや遊びをする時間を確保することが、ジュニア世代の近視予防に大きく寄与するということです。
屋内スポーツ vs. 屋外スポーツ:競技種目による視力への影響
では、同じスポーツでも「屋内で行うか」「屋外で行うか」で差はあるのでしょうか? 国際的に見ても、屋内スポーツに取り組む子どものほうが屋外スポーツをする子どもより近視率が高い傾向が示唆されています。
たとえば、中国・天津市で6〜18歳を含む若年スポーツ選手・体育系学生1401人を対象に行われた調査では、参加者の半数以上(703人, 50.2%)が近視と診断されましたが、そこからさらに競技種目ごとの近視率を比較すると、屋内競技に近視者が多いことが明らかになったのです(p<0.001) 。
具体的には、室内プールで行う水球で近視率71.4%、新体操で70.0%、バドミントンで67.2%と、いずれも屋内競技は非常に高い近視割合が報告されています 。反対に、屋外スポーツでは近視の割合が相対的に低く、統計的に見ても、屋内競技グループのほうが屋外競技グループより近視になるオッズ比が約1.788倍高いという結果でした 。
さらに、1日の練習時間が4時間を超えるようなハードトレーニングを積む選手ほど近視の割合が低かったという興味深いデータもあります 。これには、屋外で長い時間活動していることが視力保持にプラスに作用していると考えられています。
以下の表に、代表的な屋内・屋外スポーツの近視率をまとめてみました。中国・天津のスポーツ専門学校およびプロの予備軍選手を調査した先ほどのデータから屋内競技の上位例を、そして比較対象として、アメリカのユース世代(13〜15歳)の競技者を対象にした研究から屋外スポーツ2種の近視割合を示しています 。
| スポーツ種目 | 屋内/屋外 | 調査対象(地域・年齢層) | 近視の有病率(割合) |
|---|---|---|---|
| 水球(水泳プール競技) | 屋内 | 中国・天津(スポーツ選手,10代中心) | 71.4% |
| 新体操 | 屋内 | 中国・天津(スポーツ選手,10代中心) | 70.0% |
| バドミントン | 屋内 | 中国・天津(スポーツ選手,10代中心) | 67.2% |
| サッカー | 屋外 | 米国(ユース競技者,13–15歳) | 約19% |
| 野球 | 屋外 | 米国(ユース競技者,13–15歳) | 約20% |
表からも分かるように、屋内スポーツと屋外スポーツでここまで違いが出ています。ただし、中国ではそもそも対象者全体の近視率が高く、アメリカのユース世代はベースの近視率自体が低めなので、一概に数値だけを比べるのは難しい部分もあります 。それでも、「屋内競技者に近視が多く、屋外競技者に少ない」という全体的な傾向はさまざまな国の研究で一致しているというのは注目に値します 。イタリアなど別地域のアマチュア競技者を調べても「屋外スポーツほど近視が少ない」という結果が得られているため、運動そのものの効果というより、「屋外で日光を浴びながら活動するかどうか」が決定的な影響を及ぼしていると考えられるわけです。
屋外環境要因(光・視距離)と近視抑制のメカニズム
ここで気になるのが、「どうして屋外スポーツは近視を抑えるのか?」というメカニズムですよね。一般には、屋外は室内よりもはるかに明るく、遠くを見渡せる環境が広がっています。
まず日光(太陽光)を浴びることで、網膜でのドーパミン放出が促され、眼球が過度に縦方向へ伸びる(眼軸伸長する)のを抑制する働きがあると言われています 。この効果は動物実験や人の追跡調査でも支持されており、「明るい場所で過ごす」→「近視の進行を遅らせる」という流れが考えられるのです 。
また、紫外線を含む日光によるビタミンD生成や、遠景と近景を交互に見やすい屋外特有の視覚環境など、さまざまな屋外要因が複合的に視力に良い影響を与えると推測されています 。屋外では視野の奥行きが非常に広く、コントラストや空間周波数の分布が室内とは大きく異なり、発達途上の眼に入る光刺激も違ってくるようです 。要するに、自然光をたっぷり浴びて遠くを見ながら動き回ることで、眼球の過剰な伸長を防ぐ“ブレーキ”のような効果が働くと考えられます。
一方で、運動習慣そのもの(運動強度・頻度)が近視を抑える大きな要因になるかというと、実はそうではないという見方が主流です。身体活動が視力にプラスにはたらくのは、それが「屋外」で行われる場合に限られるという研究結果が多いのです 。英国のコホート研究では、運動強度よりも「屋外にいた時間」が近視抑制と相関すると示されています 。つまり、屋内スポーツを頑張っても健康面にはもちろん良いですが、近視リスクの面では屋外ほどのメリットを得られない可能性があるということです。
さらに学齢期の子どもだと、勉強やデジタル端末の使用など近距離作業が増えやすい上、屋内競技に打ち込むと放課後も日光に当たる時間がどうしても少なくなってしまう。これが屋内スポーツで近視が多い一因とも言われています。逆に、屋外スポーツなら自然と日光の下で活動する時間が確保できるので、そのぶん近視が進みづらいと考えられるわけですね。
加えて、屋外スポーツでは遠くのボールや目標を注視する機会が多く、読書やスマホのような「近距離へのピント調節」の負担が大きい作業とは対照的です。長時間の近業は調節緊張を招き近視を進行させる要因とされますが、屋外スポーツ中は遠方を見渡す時間が増えるため、そのリスクが軽減されるというのもメリットでしょう 。つまり、日光を浴びるかどうかと、視作業の距離がどうなっているか——この違いが屋内競技と屋外競技での近視リスクに大きく影響しているというわけです。
まとめ
ここまで、6〜18歳のジュニア世代におけるスポーツ参加と近視の関係について、世界各地の研究をざっと振り返ってみました。総合的に見ると、屋外スポーツをしている子どものほうが、屋内スポーツの子どもより近視が少ないという傾向が一貫して見られます 。理由はシンプルで、「屋外で過ごす時間そのもの」が近視抑制に効果を持つからです。
日光曝露の不足しがちな屋内競技では、この恩恵を受けにくいという側面があります。もっとも、スポーツをすること自体は近距離作業(スマホや読書)に費やす時間を減らしてくれるので、運動しない場合よりは近視リスクを抑える可能性もあるでしょう 。実際、「運動に多くの時間を割く選手ほど近視が少ない」という結果もあります 。
ここから見えてくるのは、「運動するかどうか」よりも「屋外でどれだけ活動するか」がポイントになるということ。屋外スポーツは、太陽の下での明るい光、遠景への視線移動、広い視野といった要素を兼ね備えています。実際に、学校の休み時間を屋外活動に充てたりする介入策が近視予防に有効だったという例も、台湾や中国の研究で示されています 。
日中2時間程度の屋外遊びやスポーツが推奨されており、成長期の子どもが屋外で体を動かすことは、視力保護の観点からも非常に有意義といえるでしょう 。もし屋内スポーツを選ぶ場合でも、できるだけ練習以外の時間に屋外へ出たり、近業と屋外活動のバランスに気をつけたり、照明環境を整えてこまめに目を休ませるよう配慮することが大切です。
結論として、世界の研究データは、「太陽の下で遠くを見る」機会が多い屋外スポーツこそが、ジュニア世代の近視進行を食い止めるうえで大きな力を発揮すると示唆しています。
参考文献・情報源
近視に関する国際的研究論文および統計データ などを参照して作成しました。
(本記事の内容は一般的な研究報告に基づく情報であり、個人の目の健康に関する具体的なアドバイスを行うものではありません。気になる症状がある場合は専門の医療機関にご相談ください。)