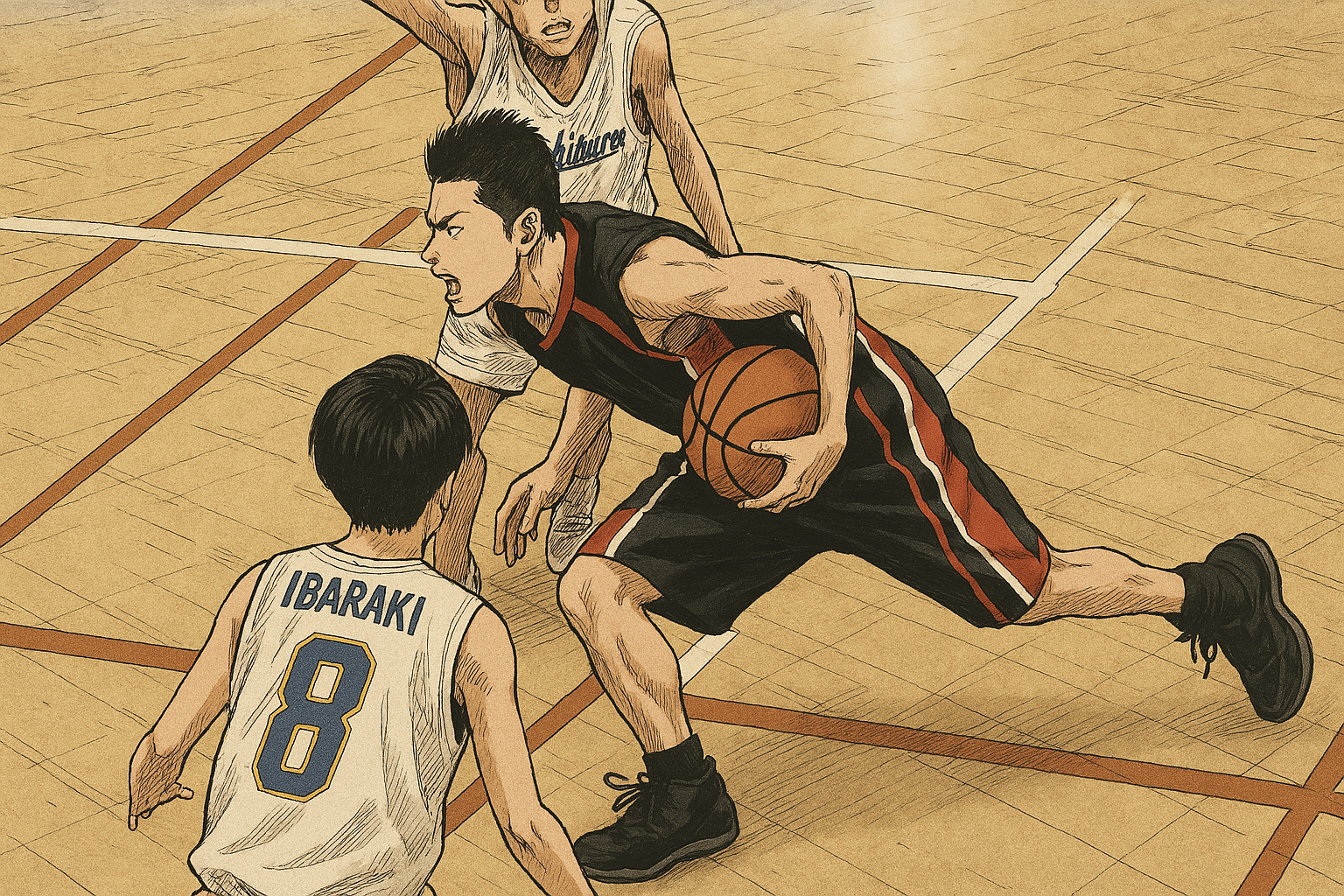はじめに
スポーツの世界において、思春期(第二次性徴)の時期が競技力や将来のキャリアに大きな影響を及ぼすことは、さまざまな研究で示唆されています。特にバスケットボールなどの競技を中心に、他の種目も含めた世界的なデータをもとに、「早熟」(=同世代よりも思春期の到来が早い選手)と「晩熟」(=思春期が遅い選手)との違いを徹底検証してみましょう。ユース年代の選抜傾向、ポジションやプレースタイルへの影響、そして最終的にどちらが有利なのか――。本記事ではその答えを探りながら、男女差や長期的なキャリアの観点も踏まえて解説していきます。
第二次性徴期(思春期)のタイミングが生む競技キャリアの分岐点
そもそも思春期の始まり方は個々によって異なります。男子ならテストステロンの増加や骨格の拡大、女子なら体脂肪の増加や骨盤幅の拡大など、身体的な変化がいつどの程度起きるかによって、スポーツパフォーマンスや指導者の評価は大きく左右されます。早熟と晩熟における長所・短所は、競技レベルの高いアスリートたちの進路にどのように作用するのでしょうか? 以下では、このテーマを深堀りします。
ユース年代における早熟・晩熟の傾向
若年選手選考の現状:早熟偏重が顕著
ユース世代(ジュニア年代)では、思春期の早い選手が一見すると「即戦力」として評価されがちです。11~15歳前後の微妙な年齢差であっても、体格や筋力は驚くほど大きな個人差を生みます。その結果、コーチやスカウトも「目先のパフォーマンスが優れている=才能がある」と捉えがちになり、早熟の選手を優先的に選抜する傾向が多くの競技で確認されています。
実際に、アイルランドのサッカーU13~U16のナショナルパスウェイを調査した結果によると、選抜選手の46~72%が早熟で、15~16歳では晩熟の選手が0%という偏りも報告されています。バスケットボールやサッカーなどの年齢別代表では、年代が上がるほどに早熟選手がより多く選ばれる現象も見られます。
一方で、競技種目による違いも存在します。男子アイスホッケーや自転車競技では早熟が有利とされる一方、男子体操では晩熟の少年の方がパフォーマンスを伸ばしやすい傾向があり、女子体操や女子フィギュアスケートでは晩熟の女子が活躍しやすいなど、一概に「早熟は絶対有利」とは言えない事情もあるのです。
競技成績・ポジション・プレースタイルへの影響
1. 身体的パフォーマンスの変化
思春期が早い選手は、少年期の段階で身長や筋力が同世代よりも突出しやすいため、スプリントや跳躍力といったパワー系テストで有利になります。たとえば13歳前後のバスケットボール選手では、早熟の選手がほぼすべての体力測定項目(スプリント・ジャンプなど)で平均的成熟度の選手を上回ったという報告が存在します。
しかし、14~15歳ごろの中~後期思春期に差しかかると、そのギャップは徐々に縮小する傾向があります。場合によっては、晩熟の選手のほうが持久力で優るなど「逆転現象」もみられます。ポーランドのU14~U15男子バスケット選手を対象とした研究でも、早熟組が平均熟成組よりも持久走や最大酸素摂取量で劣ったデータが示されています。すなわち、若年期に享受した身体的アドバンテージは永久に続くわけではないのです。
2. ポジションや役割の違い
身体発達の速さは、ユース期のポジション選択にも影響を及ぼします。サッカーでは、身長やパワーが重視されるゴールキーパーやセンターバックに早熟の選手が多く配されやすく、戦術的思考やゲームメイクが重要なミッドフィルダーには成熟度による偏りが比較的少ないという報告があります。
バスケットボールでも、成長の早い少年はサイズを買われてセンターやパワーフォワードといったポジションを担うことが多く、晩熟な選手はガードポジションでボールハンドリングやスピードを武器に戦うケースが目立ちます。実際、ユースの国際大会でも体格が優位な早熟選手はブロック数が多く、一方で体格が追いついていない選手ほどアシストやスティールといったプレーメイク面で秀でるという分析結果も。
早熟選手がパワーや高さを活かすスタイルに適性を示す一方、晩熟の選手は技術面や機動力を磨く方向に進む――こうした構図が各種競技で繰り返されているのです。
3. 競技成績への影響
ユース大会で好成績を収める選手がそのままシニアで世界的なトップアスリートになるかというと、実はそうでもありません。陸上競技の大規模研究では、U18で世界トップ100に入った選手がシニアでもトップ100入りした割合は23.5%に過ぎず、逆にシニアのトップアスリートの約68.5%がユースではトップ100外だったという結果が出ています。
これは「早熟で若年時に成功した選手ほど、その後伸び悩むケースがある」「晩熟や後発組が長期的にスキルを伸ばしシニアで大成する例が多い」ことを示唆します。バスケットボールでも、ユース時代に身体優位だった選手が成長期を過ぎると周囲との体格差が縮まり、技術・戦術理解の重要性が増す中で苦戦するケースが珍しくありません。その一方でジュニア期に苦労した晩熟の選手は、技術を研鑽しつつ心身が成熟したタイミングで一気に才能を開花させる「遅咲き(late bloomer)」となることがあるのです。
長期的なキャリアの持続性・成功への影響
1. 選手寿命と“伸びしろ”
早熟アスリートは若い頃から活躍できる反面、ピークが早まる分、その後のキャリアで壁にぶつかりやすいとも言われます。成長が早い段階で完成された選手は、その後大きな上積みが見込みにくい可能性があるのです。一方、晩熟の選手はシニア期にかけて身体的な伸びしろが大きく、20代以降に真価を発揮して長く第一線で活躍できる可能性があります。
陸上競技のデータでは、U20で目立たなかった選手ほど、シニアで世界的成功を掴む割合が高いといった結果も示されています。バスケットボールでも高校時代にパッとしなかった選手が大学で急成長し、NBAに進むという“後追い成長”のパターンは珍しくありません。
2. 離脱や燃え尽き症候群のリスク
早熟選手はユース期にエリート路線を突き進みやすく、その分ハードなトレーニングやプレッシャーにさらされる機会も増えます。結果的に故障のリスクや燃え尽き症候群に陥るリスクも高まることが指摘されています。とりわけ思春期前から特定の競技に過度に注力する“早期専門化”は、ケガの増加だけでなくマルチスポーツ経験の不足につながり、選手寿命にも悪影響を及ぼす可能性があります。
水泳では、幼少期からひとつの種目に特化した選手ほどナショナルチーム在籍期間が短く、引退が早い傾向が確認されています。一方、晩熟な選手は複数のスポーツを経験しながら自分に最適な競技やスタイルを模索し、ケガを回避しながら長期的にパフォーマンスを高めることができるかもしれません。もっとも、晩熟選手はユース期に評価されにくいため、強化の機会を十分に得られず競技を去ってしまうリスクも内在しています。この問題を解消する一例として、生物学的年齢(骨成熟度など)に応じた“Bio-banding”の導入が世界的に注目を集めています。
男女間の違い
男子選手の場合
男子はテストステロンの影響が大きいため、思春期を早く迎える選手ほど筋力や体格の面で顕著に優位となります。ユース世代では「早熟=力強い」というイメージが先行しがちですが、急激な骨格伸長やホルモン変化に伴う“思春期の不器用さ”もあり、パフォーマンスが一時的に低迷するケースもあります。
さらに、早熟の男子選手が短期的には圧倒的に強く見えても、周囲が成長して体格差が解消されると、勝負を分けるのは技術力や戦術理解度になります。したがって、早熟であることはユース期の成功を約束するわけではないのです。
女子選手の場合
女子では、体脂肪が増加し骨盤が広がるといった思春期の変化が、競技パフォーマンス面では不利に働くことがしばしばあります。そのため、一般的には早熟の女子よりも晩熟の女子のほうが、10代後半まで線が細く、スピードや持久力で優位に立ちやすいという報告があるのです。
実際、新体操やフィギュアスケートではやや晩熟の女子選手が活躍する傾向が観察され、逆にパワーや大柄な体格を要する女子水泳のような競技では早熟のほうが有利になるケースも見られます。つまり、女子の場合は「どの競技を選ぶか」によって、早熟と晩熟のメリット・デメリットが変動する点は特に重要です。
結論:早熟と晩熟、結局どちらが有利?
結論としては、「早熟にも晩熟にも利点と課題があり、一概にはどちらが絶対に有利とは言い切れない」というのが現実です。早熟の選手はユース期に身体能力で頭角を現しやすく、若い段階で高い競技レベルに達するチャンスがありますが、そのアドバンテージは思春期を過ぎると縮まる可能性が高いです。長期的に成功するには、技術や戦略眼、メンタル面の成長が欠かせません。
一方、晩熟の選手はユース期に苦労して埋もれがちですが、その過程で培った技術力や忍耐力、戦術理解を強みに、心身が完成に近づく20代以降に大きく躍進する“遅咲き”の例も多く存在します。特に技術が重視される競技では、晩熟型の方が長期的に見れば有利になるとの意見もあり、実際にデータでも晩熟選手の「後から伸びる」事例が報告されています。さらに女子の場合は、身体的な理由で晩熟が明確に有利となるシーンも珍しくありません。
とはいえ、早熟でも晩熟でも、適切な育成や指導があればトップアスリートへの道は十分開かれています。大切なのは、成熟度に応じたサポートとトレーニングの機会を整えること。早熟だからといって将来安泰ではなく、晩熟でもあきらめる必要はない――長期的な視点を持ち、選手一人ひとりの個性と成長ペースに合わせた育成を行うことこそ、アスリートの真の可能性を引き出す鍵となるでしょう。
【参照資料・引用文献一覧】
- Młyńczak et al. (2021): Effect of maturity timing on the physical performance of male Polish basketball players aged 13 to 15 years. ポーランドU13–U15男子バスケ選手818名を対象にした研究。早熟・平均熟成・晩熟の違いによる体力テスト結果を比較し、13歳以下では早熟有利、14~15歳では一部で晩熟優位が見られた。
- Arede et al.: Biological maturation in young basketball players (文献25-30等の要約)。思春期段階での身体成熟とゲームパフォーマンス(ブロック、アシスト、スティールなど)の相関を示し、早熟偏重が双方に不利を生む可能性について論じた。
- BJSMブログ (2021): 「タレント選考が将来のアスリートに与える影響 – 生物学的成熟と早期専門化の欠点」。世界各国の競技データを取り上げ、早熟・晩熟の偏りや早期専門化の弊害を解説。
- Bergeron et al. (2018): Developmental changes in the youth athlete. 早期成功が将来成功を保証しない事実や、女子では晩熟のほうが体脂肪が少なく有利になる点などを報告。水泳選手の早期専門化に関するデータも示す。
- Fort-Vanmeerhaeghe et al. (2019): 思春期の男女差をまとめた総説。男子の早熟優位、女子の晩熟優位の要因や思春期特有の不器用さ(アドレッセントピーク)について言及。
- Bezuglov et al. (2022): Successful Young Athletes Have Low Probability of Being Ranked Among the Best Senior Athletes. 世界の陸上競技者6万7千人以上を分析し、ユーストップの大半がシニアでトップに残れないデータを提示。遅咲き選手の存在を強く示唆する内容。
- Sweeney et al. (2023): A tale of two selection biases. アイルランドのユースサッカーにおける生物学的成熟度と相対年齢効果を調査。U15・U16代表で晩熟選手が0%だったなど、早熟への選考バイアスを告発し、その改善を提言している。
本記事では、早熟と晩熟のそれぞれがもたらす利点・欠点を幅広く考察しました。子どもたちが将来どのようなアスリートとして成長していくのかは、生物学的な成熟度のみならず、指導者や周囲の環境、さらには本人の意欲・努力など多彩な要因が交差した結果として現れます。早熟・晩熟を問わず、個々の特性を伸ばせるような育成・サポート体制が今後さらに求められていくことでしょう。