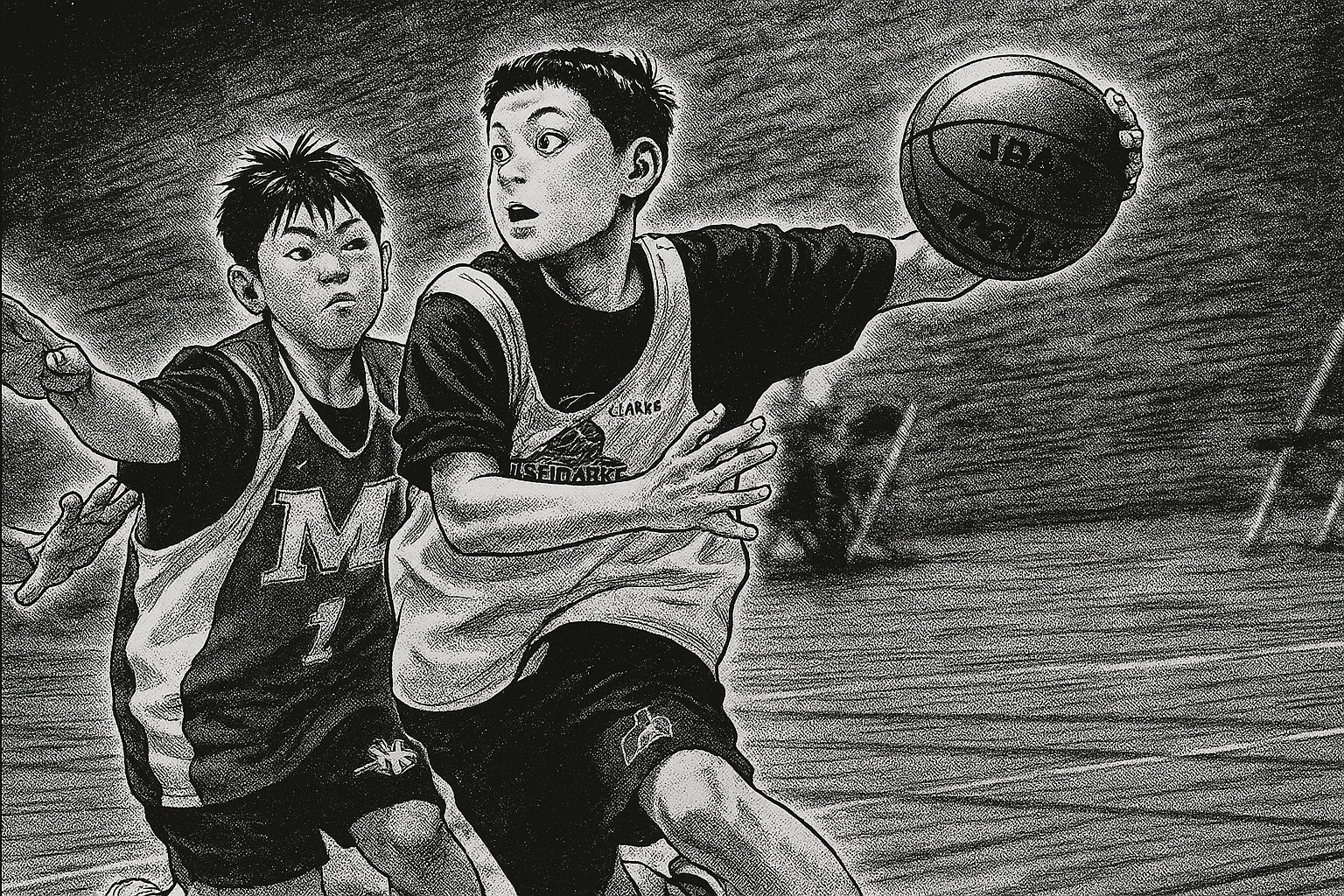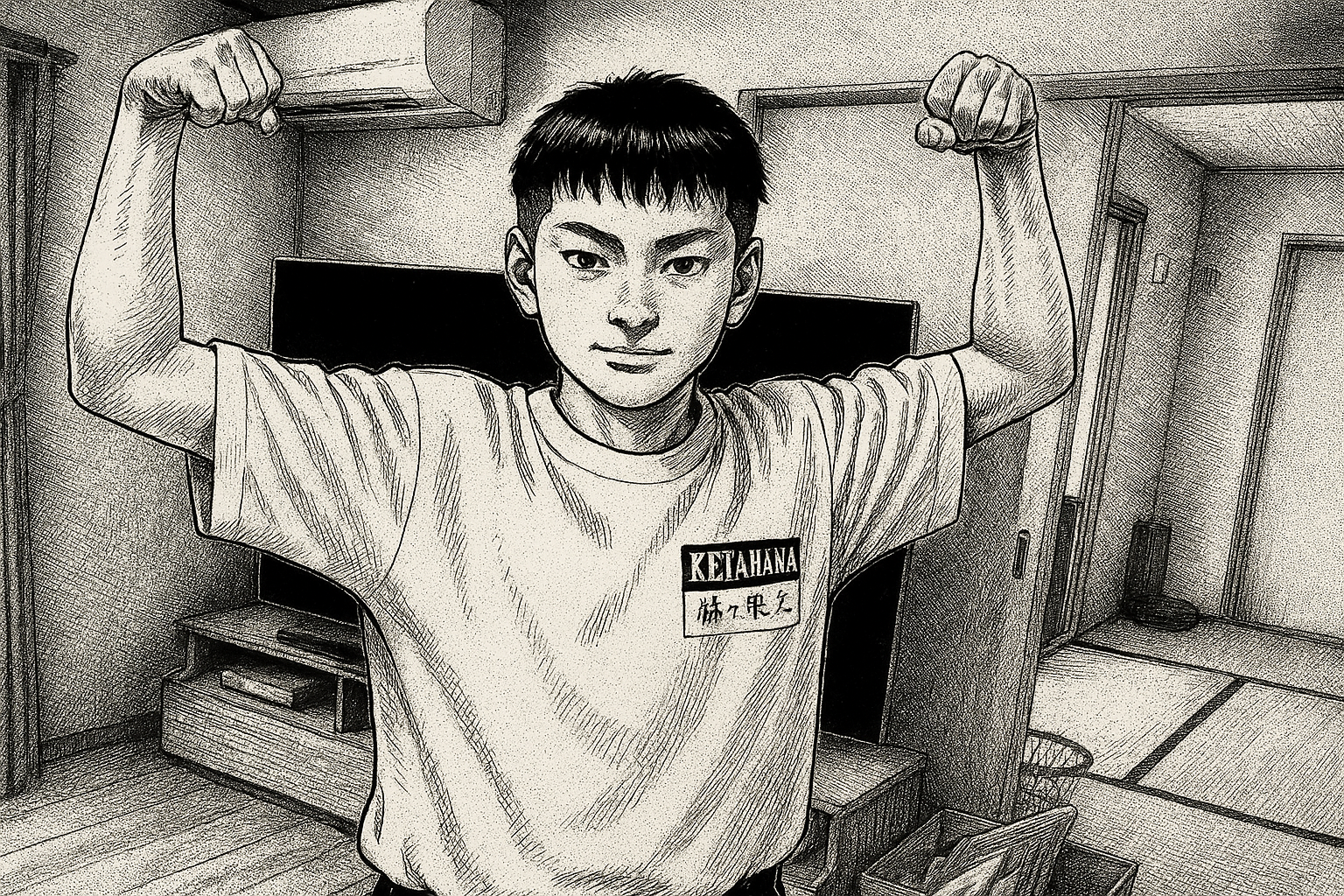幼少期に複数種目のスポーツ(マルチスポーツ)を経験することは、従来から「運動能力の土台を広げる」「ケガを減らす」「燃え尽き(バーンアウト)を防ぐ」など多くのメリットが語られてきました。一方で、幼少期から単一のスポーツに絞って英才教育を施した例(例えばタイガー・ウッズやウィリアムズ姉妹のようなケース)も成功談として知られています。この記事では、マルチスポーツ経験がアスリートのパフォーマンス向上やプロレベルでの成功に与える影響について、最新の科学的研究、統計データ、選手や指導者の証言をもとに詳しく検討します。また、マルチスポーツ経験が必ずしも有利に働かなかった例や、幼少期から単一種目に集中して成功した例についても言及し、双方を比較しながら成果・ケガのリスク・キャリア形成への影響を考察します。
マルチスポーツ vs. 早期単一競技特化:研究が示すもの
近年の研究は、幼少期からの単一競技特化(早期専門化)は必ずしも将来のエリートスポーツ成功に直結しないことを示唆しています。むしろ、多くの競技において 11~12歳以降まで様々な種目を経験し、遅れて専門化した選手の方が、最終的な競技成績やキャリアの持続期間が良好であったという報告があります 。例えば、Feeleyら(2015)の研究では、複数種目参加型(遅い専門化)の選手の方が早期に一種目特化した選手より最終的な成果が良い傾向が示されました 。また、Moeschら(2011)はエリート選手は若い頃(9~15歳)には非エリート選手より専門種目の練習時間が少ない一方、21歳頃には専門種目の練習時間が多くなる傾向を報告しており、身体的・精神的に成熟してから集中的に練習時間を増やす方が効率的とも解釈できます 。
さらに、大規模調査では、トップアスリートの多くが幼少期にマルチスポーツを経験していることが明らかになっています。Buckleyら(2017)の調査によれば、米メジャーリーグ(MLB)の選手1673人とNHL(アイスホッケー)選手58人のうち思春期までに早期専門化した選手は46%に過ぎず、平均して14.7±2.4歳で1種目に絞ったと報告しています 。裏を返せば、残り54%は思春期以降に専門化を開始しながらもプロに到達しており、早期専門化がアドバンテージとは限らないことが示唆されます 。こうした傾向は各国や競技種目によって差はあるものの、一般論として「幼少期から一つに絞らなくてもトップアスリートになれる」ことをデータが裏付けています。
一方で、早期専門化のメリットや必要性が指摘される競技も存在します。例えば、女子体操やフィギュアスケート、ダンス、スキージャンプなど競技者のピーク年齢が若かったり、幼少期から高度な技術習得が要求される種目では、早い段階でそのスポーツに集中することがエリートレベル到達のために不可欠だという報告があります 。実際、リズム体操(新体操)のエリート選手に関する研究では、エリートとサブエリートで幼少期の他競技経験数に差はなかったものの、エリートは4~16歳の期間に他競技への参加が少なく、体操の訓練時間が多かったと報告されています 。また女子体操では思春期前にピークを迎えるため、10歳前後から集中的に訓練を積む必要があるとされています 。このように競技特性によっては早期からの専門化が有利に働くケースも限定的に存在しますが、それはスポーツ全般から見ると例外といえます。多くの競技では、幼少期は様々なスポーツを経験し、中高生以降に本格的に専門種目に打ち込む方が成功例が多いのです 。
パフォーマンスとキャリアへの影響:データによる比較
では、実際にマルチスポーツ経験者と早期専門化選手で、競技成績やプロでの成功度合いに違いはあるのでしょうか。近年の研究データを比較すると、マルチスポーツ経験はパフォーマンスやキャリア面でプラスに働く場合が多いようです。
- 競技パフォーマンス・成功度:アメリカンフットボール(NFL)選手を対象にした研究では、高校時代に複数スポーツを経験した選手と一種目に専念した選手で、プロボウル(オールスター)選出率に有意な差は見られませんでした 。つまり、NFLレベルのトップ選手になるかどうかは、マルチスポーツか早期特化かに直接左右されていないことになります。一方、野球やバスケットボールではマルチスポーツ経験者の方がわずかに有利な傾向が報告されています。MLB選手の調査では、高校でマルチスポーツだった選手は、シングルスポーツだった選手よりもプロ通算出場試合数が有意に多く(平均362.8試合 vs 300.8試合、P<0.01)、メジャー昇格後の試合出場数も多かった(95.9試合 vs 71.6試合、P<0.04)ことが示されています 。NBA選手に関する調査でも、高校時代マルチスポーツだった選手は、シングルスポーツだった選手よりもプロでの総試合出場割合が高かった(78.4% vs 72.8%、P<0.01)と報告されています 。さらに、オリンピック出場選手を対象とした研究では、複数競技に関与していた選手の方が一競技専念の選手より国際大会で成功する確率が高かったとのデータもあります 。また陸上競技では、18歳以下のトップジュニアがそのままシニアのトップ50に残っている割合は男女とも20%前後に過ぎず、若い頃から国際舞台に出ていた選手はパフォーマンスの伸び悩みが見られ、より遅く頭角を現した選手の方が最終的なピーク記録が高かったとの分析があります 。これらは、若年期の早すぎる突出はその後の成長を阻む可能性を示唆しており、長期的に見れば幅広い経験を積んで段階的に専門化した方が高いピークに到達しやすいと考えられます。
- キャリアの長さ(選手寿命):競技レベルで長く活躍できるかどうかにも、幼少期の経験が影響する可能性があります。NBA選手の調査では、子供の頃にマルチスポーツだった選手の方が、データ収集時点で現役で残っている割合が高く、選手寿命が長い傾向が示されました 。対照的に、マラソンランナーでは興味深い文化差が報告されています。アフリカ出身のエリートマラソン選手は非常に若い時期にランニングへ特化する傾向があり、記録上も若い頃に競技力を伸ばしていますが、その平均引退年齢は非アフリカ選手よりも有意に若いことが示されました 。つまり、早期に競技力を伸ばした分、キャリア終了も早まっている可能性があります。一方、チームスポーツにおいては、キャリアの長さに関してマルチスポーツ経験の有無で大きな差がないとする研究もあります。NFL選手について前述の調査では、高校時代のマルチスポーツ参加か否かでプロでの在籍年数(キャリア長)には差が見られなかったと報告されています 。同様にMLS(サッカー)選手の調査でも、早期に専門化した選手ほど長くプレーできたという傾向はなく、プロ年数との関連は認められませんでした 。MLB選手でも、早期専門化組とそうでない組でメジャー/マイナー通算出場シーズン数に差はなかったとのデータがあります 。このように、キャリアの長さに関しては競技種目や個人の状況によって結果が分かれており、一概に「マルチスポーツだから長く活躍できる」「早期特化だから短命に終わる」とも言い切れません。ただし少なくとも、マルチスポーツ経験がキャリアを損なうという明確な証拠はなく、逆にいくつかの競技ではプラスまたは同等程度であることが示されています 。
ケガのリスクとメンタル面への影響
早期から一つのスポーツに絞ることは、身体的・心理的なリスク要因としてもしばしば指摘されています。複数の医療・スポーツ団体(米国整形外科スポーツ医学会AOSSM、米国小児科学会AAP、米国スポーツ医学会ACSMなど)は、近年の声明で幼少期の過度なスポーツ専門化に懸念を表明しており 、多くの専門家が「子供は一つの競技に偏らず色々な動きを経験すべきだ」と提言しています。
- ケガの発生率:複数の調査が、マルチスポーツ経験者の方がケガのリスクが低いことを示しています。NBA選手では、高校時代にマルチスポーツだった選手の方がキャリア中に大怪我を負う確率が有意に低かった(25% vs 43%、P=0.03)というデータがあります 。野球では、高校時代に一つの競技(野球)だけをしていた選手の方が複数競技をしていた選手よりも、プロ入り後に肩や肘の故障を抱える割合が高かったと報告されています 。具体的には、2008~2016年のMLB選手の分析で、高校でシングルスポーツだった選手の63%に上肢の故障歴があったのに対し、マルチスポーツ組は50%に留まったほか、投手に限ると一種目専念組の75.4%が肩・肘の障害を経験し、リトルリーグ肘などの再発率も一種目組33%に対しマルチ組17%と有意差が見られました 。また米国出身のプロ野球選手は中南米出身選手に比べ、「1種目に特化したせいで負ったケガ」を経験した割合が高かったとの調査結果もあります 。さらにウェイトリフティング(重量挙げ)やレスリングのエリート選手でも、12歳以前に専門化した選手はそうでない選手に比べ、21歳までや大学入学前までに負った大きなケガの件数が有意に多かったことが報告されています 。以上のように、早期から同じ動作を繰り返しすぎることはオーバーユース(使いすぎ)による故障リスクを高める傾向が見られます。もっとも、競技によっては差が出ない場合もあり、NFL選手の一部研究ではマルチスポーツとシングルスポーツで欠場試合数や総出場試合数(=耐久性)に有意差がなかったとの結果も出ています 。しかし概ね、発育期に様々な動きを経験して身体をバランス良く発達させた方が、特定部位への負荷が偏らずケガを減らせるという考え方が支持されています。
- 心理的影響と燃え尽き症候群:早期専門化は精神面への負担も指摘されています。幼少期から一つのスポーツだけに没頭すると、競技に対するプレッシャーやマンネリ化が生じやすく、10代で燃え尽きてしまいスポーツを辞めてしまうケースも少なくありません 。リズム体操選手の追跡研究では、幼少期に専門化を始め多く練習時間を費やした選手ほど健康状態の自己評価が低く、「楽しさ」を感じにくい傾向が報告されました 。またジュニアテニス選手の調査では、燃え尽きで競技を去った選手に共通していたのは「練習への自主性が低く、親やコーチ主導で幼い頃から追い込まれていた」ことだったといいます 。一般に、単一競技にのめり込みすぎると、心理的ストレスや競技に対する嫌気が高まり、結果的にドロップアウトのリスクが上がると指摘されています 。実際、米国のスポーツ医学界による2015年の総説でも、早期専門化はケガのリスクに加え燃え尽き症候群など心理面への悪影響が大きいと警鐘が鳴らされています 。こうした背景から「子ども時代はスポーツを楽しむ時期であるべき」「様々なスポーツの“遊び”を通じて運動技能や情熱を育むことが、結果的にトップアスリートへの土台を築く」という考えが広まっています。
マルチスポーツ経験者の成功例とその証言
マルチスポーツを経験したことがトップアスリートとしての成功に好影響を与えたと語る選手や指導者は数多く存在します。現代のエリートアスリートの育成においても、「幼少期は色々なスポーツをさせるべきだ」という風潮が強まっています。
- プロ選手の大半がマルチスポーツ出身? 例えば米国NFLでは、毎年のドラフト(新人選手選抜会議)で指名される選手の大多数が高校時代に複数スポーツをプレーしていたことが知られています。2015年のNFLドラフト指名選手256人中、実に224人(約88%)が高校で2種目以上のスポーツを経験していました 。内訳を見ると、ドラフト指名選手の63%が陸上競技、48%がバスケットボール、10%が野球にも参加していたとのデータがあります 。これは、現代のアメリカンフットボール選手の多くが他競技で培った俊敏性や跳躍力、協調性などを活かしている可能性を示唆します。USA Football(アメリカのフットボール振興団体)は若年層の育成方針として「様々なスポーツに触れることでスキルと筋力の発達につながる」と強調しており 、実際に複数スポーツ経験者はオーバーユースによるケガが少なくメンタルの燃え尽きも減るなどの利点を啓発しています 。
- トップアスリート自身の証言:プロとして活躍する選手たちも、幼少期の多種目経験の価値を証言しています。女子アイスホッケーのプロ選手を対象にした調査では、91%もの選手が「子どもの頃に他のスポーツをやっていたことがホッケー競技人生に良い影響を与えた」と回答し、誰一人「他競技が悪影響だった」と感じていませんでした 。また、2000~2012年の米国オリンピック代表選手に対するアンケートでも、約6割(59.6%)が「複数のスポーツを経験したことが競技力向上に非常に価値があった」と回答しています 。テニス界のレジェンドであるロジャー・フェデラーは、自身が子供の頃にバドミントン、バスケットボール、サッカー、スキー、水泳など多様なスポーツに親しんだ経験について語り、「幼少期に幅広く遊んだおかげで手眼の協応動作(ハンド・アイ・コーディネーション)が発達し、テニスにも役立った」と述べています 。実際フェデラーは12歳まではサッカーとテニスを両立させ、国内ジュニア大会で結果を出したのちにテニス一本に絞った経歴を持ちます 。彼は「ジュニア世代や子どもたちには、テニス以外のスポーツも楽しんで欲しい」と度々アドバイスしており、その背景には自身の体験に裏付けられた信念があります。
- 指導者や専門家の見解:指導者やスポーツ科学の専門家からも、マルチスポーツの推奨コメントが多く聞かれます。NFLの名物トレーナーであるエリック・クレッシーは「若い野球選手は秋にもボールを握るべきではない。他のスポーツをやるべきだ」と述べ、17歳までは一つのスポーツに絞らない方が良いと提言しています 。彼が嫌悪する「フォールボール(年間を通じた野球)」の習慣は、投球動作の繰り返しによる肘・肩への負担を増やし、結果としてトミー・ジョン手術(肘の靭帯再建)に至る例が多いと指摘しています 。またカナダでは「Long Term Athletic Development (LTAD)」という長期的育成モデルが国を挙げて採用されており、最終的にオリンピック金メダリストを最多輩出することを目標に、15~16歳までは複数スポーツで汎用的な運動能力を養うよう推奨しています 。このように、世界的な育成トレンドとして「早期からの一点集中ではなく、まずジェネラリスト(汎用運動能力の高い選手)を育て、その上で専門分野のスペシャリストになる」というアプローチが重要視されてきています。
マルチスポーツでも成果が出なかった例・早期特化で成功した例
マルチスポーツの利点を数多く述べましたが、全てのケースでそれが万能薬となるわけではありません。一部には「幼少期に色々なスポーツをやったけれど、それほど競技力向上に結びつかなかった」「早くから一つに絞って練習しても問題なく成功した」という例もあります。
- マルチスポーツ経験が明確な優位性を生まなかったケース:先述のNFL選手に関する研究では、プロボウル選出率やキャリア年数においてマルチスポーツ組と早期特化組で差がなかったように 、競技によってはマルチスポーツ経験が統計上顕著な差を生まないケースもあります。またサッカー(MLS)の調査でも、プロ選手として長く活躍できるかは必ずしも幼少期の専門化年齢に左右されないとの結果が得られています 。これは、一部のスポーツでは最終的に必要となる高度な専門スキルや戦術理解がものを言い、どのみちティーンエイジャー期以降に相当量の専門練習が必要なため、子ども時代の種目数は決定打にならない場合があることを示唆します。加えて、「マルチスポーツだから成功できる」というのは統計的な傾向であって、当然ながらマルチスポーツ経験者のすべてがトップアスリートになるわけではありません。そもそもプロやオリンピックレベルに到達できるのはごく一握りであり、6~17歳の競技者のうちエリートレベルに到達できるのは1%未満とのデータもあります 。この現実を踏まえれば、「マルチスポーツをやっていれば将来成功間違いなし」と短絡的に考えるのは禁物です。むしろ「マルチスポーツで幅広く基礎力を付けても最終的には各競技で必要な専門スキルを磨き上げる努力が不可欠」であり、それを怠れば能力向上に結びつかない可能性もあるのです。
- 幼少期から単一競技に集中して成功した例:対照的に、幼い頃から一つのスポーツに打ち込み成功した例も歴史上数多く存在します。その代表格がゴルフのタイガー・ウッズでしょう。タイガーは生後わずか10か月でゴルフクラブを握り、2歳で父親と毎日ゴルフの練習を始め、4歳で大会に出場、15歳で最年少の全米ジュニアアマ優勝、そして20歳でプロ転向という驚異的なエリート街道を辿りました 。同様に、テニスのセリーナ&ビーナス・ウィリアムズ姉妹も幼児期から父親の指導のもとテニス一筋の訓練を積み、後に四大大会を席巻する名選手になりました。体操のシモーネ・バイルズやフィギュアスケートのアリーナ・ザギトワなど、幼少期から専門競技に没頭してオリンピック金メダリストとなった例もあります。これらの成功者は「早期専門化の正の側面」を物語る存在ですが、専門家はしばしば**「タイガーやウィリアムズ姉妹は極めて稀な才能と環境に恵まれた“特異例”であり、万人に推奨できる育成モデルではない」と注意を促します 。実際、タイガー・ウッズの場合は幼少期からの過度な反復練習が影響したのか、30代以降は度重なる故障と手術に苦しみました** 。彼はゴルフ界で前人未踏の成功を収めた反面、そのキャリア後半は膝や腰の故障、さらには私生活でのスキャンダルも重なり低迷を経験しています 。こうした点から、近年では「タイガーの育成法はあなたの子供には真似すべきでない」といった論調も見られ 、早期特化のリスク面が強調されるようになりました。もちろん、全ての早期特化が悪い結果を招くわけではなく、競技への強い情熱を持った子供自身がそれを望み、適切な指導とサポート体制がある場合には、早い段階から才能を伸ばすことも可能でしょう。ただし、多くの指導者は「それは一部の天才児に当てはまる特殊ケースであり、平均的な子供に同じことを強制しても成功の再現性は低い」と考えています 。
結論:マルチスポーツ経験は「土台作り」と「長期的視野」で有効
幼少期にマルチスポーツを経験したアスリートは、総じて見れば運動スキルの汎用性、ケガ耐性、スポーツへの情熱維持などにおいて有利であり、それが結果的に高いパフォーマンスや充実したキャリアにつながる可能性が高いことが、様々な研究と実例から示唆されます。 特にチームスポーツや競技寿命の長い種目では、「遅咲き」の選手が頂点に立つケースも多く、幼少期の多様な経験が身体能力や戦術眼、人間的成長にプラスに働いているようです。 一方で、競技ごとの特性(例:体操のように低年齢で技能の極致に達する競技)や個人の資質によっては早期から一つの競技に打ち込む戦略も成功し得ます。ただしその場合も、ケガや燃え尽きのリスク管理や子供自身の自主性の尊重が極めて重要です。
結局のところ、「マルチスポーツ vs 早期専門化」の二者択一ではなく、幼少期・少年期には様々なスポーツや遊びを通じて運動の基礎と楽しさを培い、適切なタイミングで得意分野に焦点を絞っていくという段階的アプローチが、多くのエリートアスリート輩出において成功しているモデルだといえます。 実際、世界的に見てもジュニア期にマルチスポーツを推奨する流れが主流となっており、日本においてもスポーツ庁や指導現場で「子どもの頃は一つに絞らず色々な動きを」という提言がなされています。マルチスポーツ経験それ自体が魔法のレシピではありませんが、将来の可能性を狭めず、心身の健全な発達と長期的な競技キャリアを見据える上で、有効な土台作りになると言えるでしょう。
Sources:
- Feeley, B.T. et al. (2015), Buckley, P.S. et al. (2017) ほか
- Jayanthi, N. et al. (2013) 米国小児科学会ニュース
- Rugg, C. et al. (2018) NBA/NFL選手のマルチスポーツとケガ
- Confino, J. et al. (2019) MLB/NBA選手の競技参加調査
- 米国オリンピック・パラリンピック委員会 (USOPC) 調査
- 「Nearly 90 percent of NFL Draft selections played multiple sports in high school」Joe Frollo (2015)
- 「The Tiger Woods Model Is Not for Your Kid」Shane Trotter (2021)
- ロジャー・フェデラー幼少期エピソード(Wikipedia)