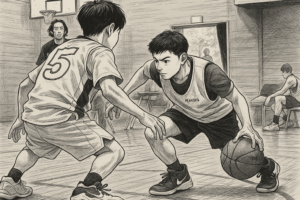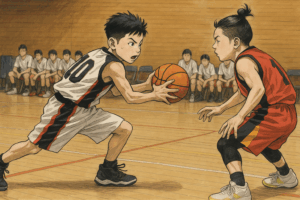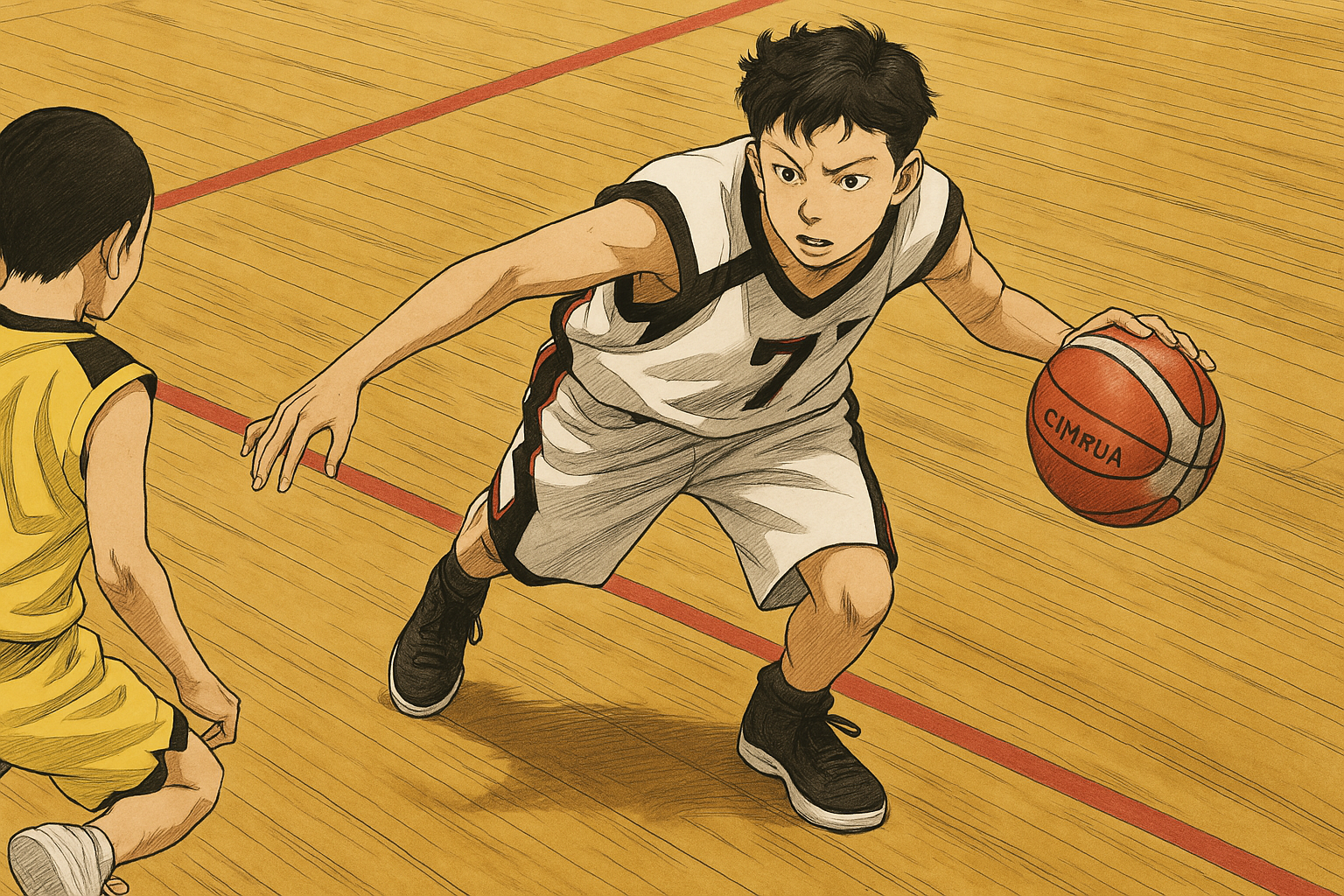こんにちは!今回は、「先天的才能がものを言う競技」と「後天的な伸びしろが大きい競技」を、それぞれランキング形式でご紹介していきたいと思います。スポーツにはさまざまな種目がありますが、身長や筋力など“持って生まれたもの”が大きく影響するタイプと、努力や練習次第でどこまでも伸びられるタイプが存在しますよね。そこで、両方の視点から代表的な競技をピックアップしてみました。最後には全体の比較やまとめも載せていますので、ぜひ最後まで読んでみてください!
先天的才能がものを言う競技ランキング
1. バスケットボール(バスケ) – 「高さ」は絶対的な武器
バスケではゴールの高さやリバウンドの争いといった要素があるため、身長や腕の長さといった先天的な体格が大きなアドバンテージになります。実際、NBA選手の約7分の1は身長213cm(7フィート)以上ですが、一般人がその高さに達する確率は約65万分の1という超狭き門 。さらに、身長が1インチ(約2.54cm)高くなるごとにNBA入りの可能性が約2倍になるという統計もあるんです。一方で、約178cm以下ではNBAに到達できる可能性が380万分の1と極めて低いというデータもあります 。
こうしたことから、バスケは「高さ」やリーチといった遺伝的要素が競技適性を左右する典型例と言えるでしょう。いくら後天的に努力しても“高さ”だけは「教えられない(You can’t teach height)」という有名な言葉があるように、どうしても生まれ持った体格差が響きます。一方でシュート技術や戦術理解などの後天的要素も重要ではあるものの、トップレベルに達するにはまず恵まれた体格が前提条件となっているのが現実です 。
2. 短距離走(100m走) – 「瞬発力」は生まれつきの資質
100mなどの陸上短距離では、先天的に持っている筋肉のタイプ(速筋線維の割合)や反応速度が記録を大きく左右します。トップスプリンターの筋肉は約70%が速筋で構成され、一般人の約50%に比べて圧倒的に高速収縮に特化していると言われています 。さらに、速筋能力に関与するACTN3遺伝子との関連性も知られており、エリート短距離選手の女性には「XX型」遺伝子(速筋タンパク質が欠損するタイプ)が一人もいなかったという報告もあるほど 。
こうしたことから、「スプリンターは生まれついてスプリンター」というフレーズがあるように、先天的な筋力・スピードの才能がないと世界レベルでは戦いにくい競技となっています。よく「スピードは神からの贈り物(才能)であり、教えることはできない」と言われるように 、瞬発力は後天的な鍛錬だけでは埋めきれない部分が大きいんですよね。しかしもちろん、才能があってもそれを最大限に活かすためには徹底したトレーニングが必要であり、才能×努力の掛け算でこそトップレベルに到達するというわけです。
3. ウェイトリフティング(重量挙げ) – 筋力とパワーの遺伝的ポテンシャル
重量挙げでは、バーベルを一瞬で持ち上げる爆発的パワーが求められます。ここには筋繊維のタイプや筋力の素質といった先天的要因が強く関わってくるんです。エリート重量挙げ選手の筋肉は、極めて速筋線維の割合が高く、短時間で大きな力を発揮する“速筋優位”の筋構造を持っています 。トップレベルのリフターだと、筋繊維の7割前後が速筋という報告もあるほどで、その遺伝的な筋力の上限値が非常に高い人がやはり世界の舞台を席巻しています 。
また、骨格の違い(胴体や四肢の長さの比率など)も重量の挙上効率に大きく影響します。結局のところ、こうした生まれ持った体格・筋力ポテンシャルが際立っている選手が、世界記録級のリフターになる土台を持っているわけですね。もちろんテクニックや神経系の適応など長年の練習も不可欠ですが、先天的なパワーの才能がなければ限界レベルの記録を更新するのは厳しい競技と言えます。
4. 水泳(競泳) – 生まれ持った「水泳体型」と身体特性
競泳、とくに短距離の自由形やバタフライでは、身体的特徴がダイレクトにタイムに影響します。オリンピックの競泳選手を見ると、高身長で腕が長い選手が多いですよね。これは、リーチ(ウイングスパン)が大きいほど推進力を稼ぎやすいからです。実際、腕の長さが身長に比べて相対的に長い選手ほど有利という報告があり、そのおかげで自由形や背泳ぎでも高成績を収めやすいと言われています 。
さらに、水泳向きの体格として「脚が短めで胴が長い」「三角形の上半身」「手足が大きい」「肺活量が大きい」なども挙げられます 。こうした特徴は先天的に決まる部分が大きく、大きな手足は水をかく“パドル”や“フィン”の役割を担い、肺が大きいと浮力と持久力が高まりやすいんです 。加えて、肩や足首の柔軟性が高い(関節が非常に柔らかい)ことも競泳の大きなアドバンテージになり 、こうした柔軟性も遺伝の影響を受けやすいとされます。
五輪金メダリストのマイケル・フェルプス選手は、身長193cmに対して腕長201cmという驚異のリーチを持ち、足サイズも33cm超(サイズ14)という“水かき”のような体型です。さらに、乳酸の産生量が少ないという特殊体質まで兼ね備えており 、まさに水泳向きの先天的身体能力で大活躍した典型例ですね。とはいえ、もちろんスタートやターンの技術、フォームの反復練習など後天的な努力も欠かせません。才能×努力で記録を伸ばす競技としての魅力があります。
5. 体操競技(体操) – 選ばれし体格と瞬発系センス
体操(特に女子)は小柄で軽量な体格や高い柔軟性といった先天的特徴を持つ選手が圧倒的に有利だとされています。世界のエリート体操選手は、一般人と比べて身長が低く体重も軽い傾向がありながら筋肉質で、脂肪が少ない体型(外骨格-中骨格型)に集中しているという調査結果があるんです 。女子の平均身長は140~160cm程度が多く(東京五輪女子体操メダリストの平均身長は約155cm )、男子でも170cm未満が主流。こうした小柄な体格だと回転系の技を出しやすく、空中での姿勢制御もしやすくなるわけです。
さらに、関節の可動域の広さや平衡感覚などは遺伝的影響の強い「センス」の部分も多く、幼少期から突出している選手ほどエリート候補として選抜される傾向にあります 。実際、トップレベルの体操選手は、ある意味「体操向きに生まれついた身体」の持ち主だという報告もあるほど。ただし体操では非常に高度な技術が求められるため、小柄であれば良いというだけでなく、幼少期からの厳しいトレーニングが必須です。先天的な資質+長年の専門的鍛錬で初めてオリンピック級の演技が可能になる、そんな競技なんですね。
後天的な伸びしろが大きい競技ランキング
1. 射撃(クレー射撃・ライフル射撃など) – 年齢や遅いスタートを克服できる技術競技
射撃は瞬発力や筋力よりも、精密な技術と集中力がモノを言う競技です。そのため、後天的な練習量による上達の幅が非常に大きく、比較的遅い年齢から始めてもトップレベルに達しやすいという魅力があります。実例としては、イランのジャバド・フォルギ選手が37歳で本格的に射撃をスタートし、わずか4年後の41歳で東京五輪ピストル種目の金メダルを獲得しました 。これは射撃が加齢による肉体的衰えよりも経験や技術の蓄積のほうが重視される証拠と言えるでしょう。
また、スウェーデンのオスカー・スワン選手は72歳でオリンピックに出場して銀メダル、64歳では金メダルを獲得したという驚きの記録すら残しています 。こうした例を見ても分かるとおり、射撃では「後天的な練習の積み重ね」が最も重要で、メンタルコントロールや集中力の鍛錬も勝敗を左右します。先天的な要素がゼロとは言えず、視力や手先の安定性が有利に働く場合はあるものの、やはり技術面と経験値による伸びしろが大きい典型的な競技と言えそうです。
2. アーチェリー(弓道) – 体系化された訓練で誰もが伸びる余地
アーチェリーも射撃に似て、技術とメンタルが重要視される競技。幼少期から体系立てたトレーニングを積むことで大きく成績を伸ばすことが可能です。中でも韓国は科学的な育成システムで知られており、1984年以降のオリンピックアーチェリーでは45個中27個もの金メダルを獲得するほどの圧倒的強国 。小学校から厳しい選抜と鍛錬を始めるため、国内代表になるだけでも「五輪で金を取るより難しい」と言われるほど競争が熾烈ですが 、その徹底した育成こそが常勝の秘密と言われています。
実際、東京五輪で17歳にして2冠に輝いたキム・ジェドク選手は、小学校高学年で弓を始めてからわずか8年足らずで金メダリストに上りつめました 。これはアーチェリーにおける後天的訓練の伸びしろを象徴するエピソードですよね。過度な筋力や身長はそこまで必要ではなく、安定したフォームや平常心を養う訓練が中心。先天的な視力や器用さがあれば有利ですが、トップレベルの選手はみな長年の反復練習で精密な射型を身体に染み込ませており、努力こそが強さを支えている好例と言えます。
3. ゴルフ – 「練習量」がスコアに直結する生涯競技
ゴルフは体格や瞬発力よりも、ショット技術・メンタル・コース戦略が重要になってきます。そのため後天的な練習や経験によって着実に向上できる競技と言えるでしょう。トッププロでも何年もかけて技術を研鑽し続け、他競技と比べるとピーク年齢も高め。メジャー大会の最年長優勝記録が、フィル・ミケルソン選手の50歳(2021年の全米プロ)というのは驚きですよね 。彼は40代後半からも飛距離や技術を進化させ続け、50歳でメジャーを制覇してしまいました。
こうした事例が示すように、ゴルフは年齢を重ねても成長し続けられるスポーツで、若い頃に特別な才能がなかった人でも練習を積み上げればトップレベルに近づける可能性を秘めています。プロゴルファーは膨大な打ち込み練習やコース経験を積み重ねることでスコアを縮め、「練習すればするほど運(結果)が良くなる」という有名な格言 を体現していますよね。先天的な空間認識力や手先の感覚なども影響しないわけではありませんが、体格差のハンデが比較的小さい分だけ努力がスコアに反映されやすいのも魅力。体力や柔軟性はトレーニングで補いやすく、「才能より努力がモノを言う」代表的プロスポーツと言えるかもしれません。
4. マラソン(長距離走) – 鍛錬による持久力向上で大躍進可能
マラソンは人間の持久力の極限に挑む競技ですが、この持久力(有酸素運動能力)はトレーニング次第で大幅に向上させられるのがポイント。トラック短距離に比べて、才能よりも努力が占める割合が高いとされ、長年の積み重ねで着実に記録を伸ばせるため「後天的伸びしろ」が大きい種目だと考えられています。実際、マラソンのトップ選手のピーク年齢は他の陸上種目より高めで、男子だと30~37歳あたりで自己ベストを出す選手が多いとの分析があります 。
世界記録保持者のエリウド・キプチョゲ選手も33歳で当時の世界記録を樹立し、35歳で2時間1分台前半という驚異的タイムをマークしました 。こうした30代以降に全盛期を迎える例が多いことは、長年のトレーニング蓄積が記録に直結している何よりの証拠 。心肺機能や筋持久力、ランニングエコノミーは適切な反復練習で大きく強化できるので、一般的な体格や能力の人でも努力次第でサブ3(3時間切り)を達成したり、エリートランナーに近づくことが可能なのです。一方で、高地順応能力やランニング経済性など先天的な要素も確かに存在しますが、そうしたハンデを戦略や鍛錬で補いやすいのがマラソンの特徴でもあります。
5. サッカー(フットボール) – 多様なタイプが努力で花開く世界スポーツ
サッカーは世界中でプレーされているだけあって、成功する選手のタイプも実にさまざま。身長や体格が小さくても大きくても活躍できる余地が大きい競技なんです。たとえばリオネル・メッシ選手(169cm)やシャビ選手(170cm)のように小柄でも、抜群の技術と戦術眼で世界最高峰の舞台へ上り詰めることができますし、クリスティアーノ・ロナウド選手(187cm)のように体格に恵まれた選手が自身の努力でスキルを伸ばし続けるパターンもあります。
サッカーでは幼少期からのボールタッチ練習や戦術理解の積み重ねが極めて重要で、プロ選手の多くはユース時代に1万時間以上のトレーニングをこなして技術を磨き上げているそうです。実際、「才能が少しでもあればハードワークが才能に勝る」という言葉があるように 、プロとして活躍できるレベルに限れば努力によって才能の差をひっくり返すケースも少なくありません。また、サッカー界には相対的年齢効果(同じ学年内で早生まれが有利になりやすい現象)も顕著に見られ 、選手の育成においては誕生月による体格差や成長差が選抜に強く影響していると報告されています 。これは生得的な才能よりも、育成年代の環境や指導法が将来のスターを生む大きな要因になることを示唆しています。
もちろんトップレベルではボールコントロールのセンスや判断力など先天的才能がずば抜けた選手がスターになる傾向がありますが、それでも彼らは幼少時代から人並外れた練習量をこなしているのが現実。要するに「才能と努力のハイブリッド」こそが世界を魅了する選手を生むわけです。いずれにしてもサッカーの場合、才能の種類が多岐にわたるため一概に先天的資質だけで決まることは少なく、後天的な練習・経験の差がピッチでの明暗を分けやすいと言えるでしょう。
比較考察・まとめ
以上、「先天的才能がものを言う」スポーツと「後天的な伸びしろが大きい」スポーツを比較しながらご紹介してみました。前者(バスケや短距離走など)では、競技特性に合った強力な遺伝的素質(高さや瞬発力)が早い段階で選手の“天井”を決定づけてしまう傾向があります。極端に言えば、才能のある者だけがスタートラインに立ちやすく、才能がなければいくら努力してもトップ層には食い込めないという「残酷さ」があるとも言えます 。
一方、後者(ゴルフや射撃、マラソンなど)は、必ずしも恵まれた体格や身体能力がなくても、訓練や工夫次第で大きなパフォーマンス向上が見込めるジャンル。年齢や身体的ハンデを覆して遅咲きで成功するアスリートも多く、努力が報われやすい分野とも言えるでしょう。
もっとも、多くのスポーツでは先天的才能と後天的努力の両方が合わさってこそ世界の頂点に立てるのも事実 。スポーツ科学的にも遺伝と環境の割合は競技ごとに大きく変化し(たとえば体操と100m走を比べるなど)、エリート選手の育成には両要素の最適な組み合わせが必要だとされています 。つまり、才能が高いほど努力による伸びしろも高くなりがちで、最終的にオリンピックやプロのトップクラスへ行くには「才能を持った選手が猛烈な努力をする」のが大前提。逆に言えば、才能だけでも頭打ちになりますし、努力だけでも限界を突破できないというシビアな面もあるんですよね。
総じて、
- 「先天的才能がものを言う競技」では、身長や筋繊維タイプといった特徴が勝敗やレベル差を大きく左右し、そうした才能のある選手同士でトレーニングや戦術理解などの後天的要素が勝負を分ける。
- 「後天的な伸びしろが大きい競技」では、多様な人材に門戸が開かれており、努力や経験を積むことで実力を飛躍的に伸ばしやすい。
といった特徴があります 。前者の競技ではタレント発掘が重視され、後者の競技では育成システムや環境整備が重要視されることが多いでしょう 。とはいえ、どの競技でもメンタル面をはじめ、後天的に成長できる部分も必ずあるので、先天×後天が複雑に絡み合ってアスリートのパフォーマンスを支えているといえそうです。
参考文献・情報源:遺伝子とスポーツパフォーマンスに関する科学的研究 、スポーツ遺伝学・人類学的調査 、欧米のスポーツ統計データ 、選手・指導者のコメント などを参照しました。スポーツの世界は本当に奥が深いですね!皆さんもぜひ、自分の得意や好きな競技に合わせてトレーニングしてみてください。何かしらのヒントになるかもしれませんよ。